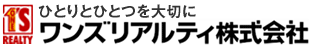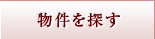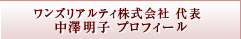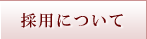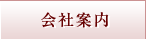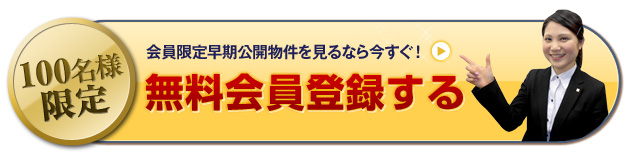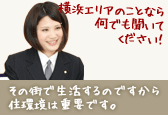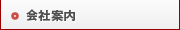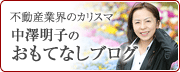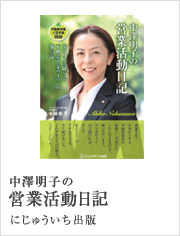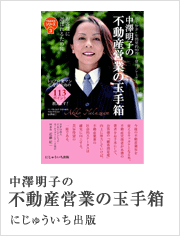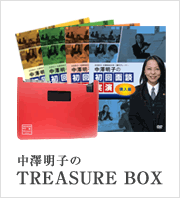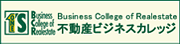登録物件数
- 一般公開物件:4件
- 会員限定物件:0件
会員ログイン
ワンズリアルティ株式会社
スタッフブログ
2016年08月28日営業活動日記 「段取り8割と見える化の重要性」

皆様、こんにちは。西村友里です。
今日は、初めてお目にかかるオーナー様宅を訪問して参りました。こちらのオーナー様のマンションを弊社で管理させていただいておりますが、
7年間お住まいだった入居者様が退去されたため、内装工事のご承諾を頂くために訪問いたしました。
今回の内装工事費には、レンジフードの交換等も入っているため金額が嵩みました。
そのため、オーナー様に上手に説明をすることができるか、スムーズにご承諾を頂くことが
できるかと不安でした。
輪をかけて台風が近づいているということで余計に不安が募っていました。
元々代表のお客様ですので、代表は何度もオーナー様とお会いしています。
そのため、私が不安そうにしているのを見かねた代表から、「大丈夫よ!すごく優しい方だから。」と
言葉をかけて頂きましたが、私がオーナー様へアポイントをとる電話をした際に工事費用が
掛かるお話をしたところ、オーナー様の声のトーンが下がったことが気になっておりました。
不謹慎ではありますが、台風で訪問が延期にならないかとまで思ってしまいました。
緊張しながらも、お約束の時間に遅れないように会社を出発しました。
お会いしたらまずご挨拶をして、台風の話題を出してから内装工事の説明をしようと
頭の中でシミュレーションしながら向かいました。
迷うことなくオーナー様宅の最寄りのバス停まで辿り着きましたが、バスを降りた瞬間、
いきなり強い雨が降ってきたので、落ち着きつつあった心が再び不安へと変わってしまいました。
早く到着したため、オーナー様宅の周辺を探索して、このエリアがどういうところなのかを観察しておりました。
通りがかった親子に「こんにちは」と、笑顔で挨拶をしたのですが、大雨の中、住宅街をウロウロしている
制服姿の私を不審に思ったのか、目も合わさずにスルーされてしまいました。
「落ち込んではいけない!元気にいこう!」と、自分で自分を奮い立たせて、オーナー様宅の呼鈴を押しました。
すると、とても優しそうな白鬚の男性が出て来られて、ご自宅へと招き入れてくださいました。
リビングにいらっしゃった奥様もとても優しそうな方でしたので、私は頭で描いていた会話をスムーズに
行うことが出来ました。
代表の口癖である「段取り8割」という言葉通り、見える化した書類と写真を用意して説明を行ったため、
無事に内装工事の承諾を頂くことができました。
オーナー様は、すぐにその場でネットを使って工事費用をお支払い下さり、迅速な対応で業務が完了致しました。
頭の中でのシミュレーションと見える化した資料がなければ、今の私の未熟な提案力では、
きっとご理解頂けなかったことと思います。
スムーズに終えることが出来たのも、見える化した書類を持参した結果です。
今後も段取り8割を忘れずに、自分に自信をつけてまいります。
カテゴリー: スタッフブログ
Comments Off on 営業活動日記 「段取り8割と見える化の重要性」
2016年08月27日今日の玉手箱 「宅地建物取引士の誕生」

皆様、こんにちは。中澤明子です。
今日の玉手箱「宅地建物取引士の誕生」
ご存知の通り、不動産業界もようやく弁護士や会計士など専門資格の職業を意味する、
「士業」の仲間入りを果たしました。
お客様の大切な財産を管理する仕事なのに、「なぜこんなに遅かったのか」というのが、
私の中での疑問点ではありますが、名称が変わったことにより「志を高くもった業界人」が
増えることを期待したいと思います。
「宅地建物取引士」が誕生したといっても、まったく新しい国家資格が誕生したわけではありません。
不動産流通の円滑化を目的に制定された宅地建物取引業法を改正し、これまでの「宅地建物取引主任者」を
改称したわけですが、「取引主任者」と「取引士」では大きな違いがあることを、私たち不動産業に携わる者は
意識をし業務に臨まなければなりません。
◇「重要事項説明」の不実告知
不動産業界では、紛争相談の3割が「重要事項説明」の不実告知にあると言われています。
もちろん、人が調査を行うのですから、調査する人の能力や質問の仕方、物の見方等により、
調査ミスや調査漏れなどが発生するのは仕方がないことだと考える人がいるかもしれませんが、
プロとして決して許されることではありません。
売買仲介の場合、不動産会社と売主様との連携が重要な業務のひとつです。
例えば、役所調査だけではわからないことでも、所有者である売主様がわかっていることや、
保管している資料や情報などがあります。
これらのことも重要事項に反映させるのが私たちの役割です。
遡ること、宅地建物取引主任者の名称が初めて法律に盛り込まれたのは1964年です。
そして1971年に取引主任者による購入物件に関する重要事項説明と契約締結時の書面交付が義務づけられました。
1980年に、維持向上を図ることを目的とした、法定講習制度が創設され、5年に一度の免許更新時に、
講習で改正法令や紛争事例などの最新情報を学ぶことが定められました。
しかし、実際には5年に一度の法定講習は長すぎます。
中には法定講習を面倒くさいとか必要性がないものと判断している宅建業務の従事者もいるようですが、
これはもう問題外です。
法律や税制などは毎年何かしらの変化があります。
もちろん、プロですから法定講習に頼らずとも、日常アンテナを張って、努力を積み重ねて
勉強するのが当たり前です。
重要事項説明に関するトラブルが多発していることを考えると、プロとして仕事にプライドと誇りを持って
一般消費者のために臨んでいるのではないことが理由のひとつではないかと思います。
カテゴリー: スタッフブログ
Comments Off on 今日の玉手箱 「宅地建物取引士の誕生」
2016年08月26日営業活動日記 「ぶれない精神力」

皆様、こんにちは。西村友里です
気が付けば8月も残り5日となりました。
毎日密度の濃い仕事をしているため、1日が終わるスピードが以前にも増して
早くなり、焦ってしまいます。
それだけ、私にできる仕事が増えた結果であると嬉しく感じています。
営業マンとしては、あっという間に月末がくるので締日を考えると慌ててしまいます。
また、今月は月初に行っている巡回点検も頭から抜け落ちており、本日急きょ巡回点検を行って参りました。
しかし、数件をまとめて行ったため、私の足が悲鳴を上げました。
仕事は溜めるものではないことを改めて痛感しました。
以前の日記でも書かせて頂きましたが、管理物件の近くにあるお寺に貼られている
お言葉が今日は、「楽しいことをやろうとするのではなく 今やっていることを楽しむことが大事」とありました。
思わず「なるほどな!」と思いました。
また、『楽しく生きたい人に絶対読んでほしい人生哲学』というインターネットサイトでは、
「大事なのは意識ある選択と行動」と書いてありました。そして、『日本人はもともと保守的な民族ですから、「安定」「安全」という甘い言葉に惹かれやすいのです。
「やりたいことをやる」とか、「挑戦」とか、「楽しく仕事する」とかをものすごく嫌うでしょう。
より安全で堅実な生き方を信じます。
もちろん、それが自分の実力を見極め、きっちり努力を重ね、運や縁を経てたどり着いた結果なら、
なにも後悔はないでしょう。苦労はもちろんそれなりに有るでしょうが、ぐちぐち言うことはありません。
今の日本社会の最大の勘違いは、「仕事とは苦痛なもの、めんどくさいもの」
「やりたいことをやる=楽(らく)」、「挑戦しない堅実な人生=安全」という固定概念に他なりません。
仕事を楽しんでいる仕事人はたくさん居ます。
それできちんと結果を出している人もたくさん居ます。
やりたいことをやる人生は楽でしょうか。違います。
やりたいことをやろうとすれば、それを達成するための苦労があります。
文句も言われます。
「失敗しないためには挑戦しなきゃいい。何もせず無難に生きよう」
違います。
何十年か生きていれば誰でもほんとうは知っているのです。無難な人生なんて無いということ。
むしろ、怠けていれば怠けているだけ、あとあと自分が後悔するのです。虚しくなるのです。
天才でも秀才でも凡才でも、だれでも失敗するし、挫折するし、不快な想いをするし、悩むし、落ち込むし、疲れます。
それは、どんなに安全に生きようとしても変わりません。
失敗や悩みの大小だって、他人とは比べられないものです。大事なのは、現実を受け入れること。
現実的に考えることです。
人はそれぞれ、変えようの無い生まれや育ち、家族・親族、体質、気質、トラウマ、悩み、能力、好き嫌いと、
色々な事情を抱えて生きていますでしょう。
誰もが同じように生きられるわけではありません。
同じだけ努力すれば必ず同じところに到達できるわけではありません。
そういう当たり前のことを受け入れた上で、きちんと選択することです。
自分という人間を見極めて、それに沿った目標設定をする。
その目標に向けて失敗を繰り返しながら努力をする。
成長を楽しむ。小さな成功の一つ一つを楽しむ。
結局はそれが出来るかどうかなのです。
それが出来る人は、そこそこ人生楽しいはずです。』 ※楽しく生きたい人に絶対読んでほしい人生哲学より抜粋
仕事もプライベートも、人それぞれいろいろな事があると思いますが、
大変な状況下でもプラス思考に物事を考え、「これは自分がステップアップするためのチャンスなのだ」と思えば、
何でも乗り越えられる気がします。また、営業は相手がある仕事ですので、お客様との会話や出会いが
私を元気にしてくれます。おかげさまで、私は毎日楽しく不動産の仕事をしております。
これからもブレない精神力を養いながら、日々精進いたします。賃貸のことなら、ぜひ西村友里にお任せ下さい。
カテゴリー: スタッフブログ
Comments Off on 営業活動日記 「ぶれない精神力」
2016年08月25日今日の玉手箱 「チャンスは自らの手でつかむもの」

皆様、こんにちは。中澤明子です。
今日の玉手箱「チャンスは自らの手でつかむもの」
人と人との係わり合いは、とても重要です。
年を重ねるごとに、本来その重要性をわかっていて当り前なのですが、
歩んできた道や環境、価値観などが異なると、悲しいかな、
わからない人もいるものです。
自己中心的で、相手の気持ちを理解できない人との出会いほど、
虚しいことはありません。
自らが協力を求めてきたにも拘らず、それに応えた途端に手の平を返して、
平気で不義理をした人と出会ったこともありました。
数年ぶりに訪ねてきたため、懐かしさもあり、何とか助けてあげたいという一心から
最良のかたちをつくり協力したのですが、事がうまくいったのは自らの運の強さだと
勘違いをして去っていきました。
逆もありました。事がうまくいかないのは会社や上司の責任だと。
感謝ができない、お詫びができない大人ほど見苦しく、情けないものはありません。
客観的に物事を判断することができない人をみると悲しくなります。
このような人は、自分に協力をしてくれている人は誰なのかを冷静に見極めるべきです。
自らの力だと思った瞬間から、人との縁は切れます。
せっかく築いてきた信用もチャンスも、自らの手で壊すのですから、
本人にとっては、それはそれで良いのかも知れませんが。
自分さえよければそれでいい。
そんな人の味方に誰がなるのでしょうか。
それに気付かないまま時を重ね、振り返ったときには誰もそばにいない。
気付いたときには遅いのですが、それもその人の人生。
誰も恨むことはできません。
他人の評価は厳しいものです。
自己満足だけで生きられるのであれば、そんな楽なことはありません。
人は支えあって生きているのですから、自分一人では生きられないことに早く気付くべきです。
自分の力を過信することなく、ある程度の年齢になったら謙虚にならなければ、人はついてきません。
「立つ鳥跡を濁さず」人として大切なことであると私は思います。
カテゴリー: スタッフブログ
Comments Off on 今日の玉手箱 「チャンスは自らの手でつかむもの」
2016年08月23日営業活動日記 「子供の『気』」

皆様、こんにちは。西村友里です。
長年お世話になっておりますオーナー様から、
弊社の代表宛にお電話を頂きました。
定期的にお電話くださるオーナー様ですが、偶に「日記見たよ!」と
先輩や私にも日記の感想をお話してくださる、とても温和なオーナー様です。
あいにく、代表は京都で講演を行うため出張しておりましたので、代表への伝言を承り、
私は管理頂いているアパートや募集をさせて頂いている事務所の現状報告を致しました。
募集している事務所は反響こそ多いのですが、なにぶん反響の多くは、
ビルオーナー様が却下される保育園を希望する問合わせばかりです。
このことをお伝えしたところ、オーナー様から子供の「気」について、とても興味深いお話を伺いました。
ビルオーナー様が保育園を断る理由は、こちらのビルには一般企業が多く入っているので、
その方たちに何かしらの影響を与えてしまわないか危惧されているからです。
決して子供を苦手としているわけではありません。
オーナー様いわく、「子供には元気な「気」が流れているので、大人は握手等のスキンシップをとって
その気をもらうと良い。逆に子供にとっては、その気が多すぎると元気さが有り余り、喚いたり暴れたりする。
そのため、互いにスキンシップを図ることが双方にとって良い。」のだそうです。
以前、他のお客様からも「幼稚園や小学校の近くに住むと良い。そこには元気なパワーが集まっているから、
良い気がまわってくる。」と教えて頂いたことがありました。
広島弁護士会に所属されております、山下江法律事務所の山下弁護士は、自身の日記で
次のように記載されています。
「昨日(7月5日)午前9時から1時間くらい、次女の通学する小学校で運動会の反省会などPTAの集まりがあった。ぼくは、PTA副会長として参加した。校長先生や教頭先生も加わり、
30人くらいの参加者は、活発に意見を出し合った。そのときの校長先生の挨拶がなかなか良かった。金子みすゞ記念館館長矢崎節夫氏が講演で、「子ども浴」の話をされたのを聞いたことがある。
「日光浴、森林浴とかあるが、先生方は、毎日子どもから大きなパワーを受けている。
これは、子ども浴だ。だから、若さを維持できる。」と。
同校長先生の先輩から届いた年賀状にも、同様の趣旨が記載されていたと。
「最近、パワースポットなるものが流行っているが、究極のパワースポットは、幼稚園や保育園等の子どもたちの集まる場所ではないか。子どもたちはそこにいるだけで、周りを明るくし、パワーをくれる。」
(一部省略)
校長先生が就任された5年前には、学校は結構荒れていたらしいが、最近は非常によくなったとのこと。
教育がこんなにも状況を変えるのかと関心した。」と記載されていました。
弊社本店のビルの中にも、最近保育園ができました。
私も子供は好きですが、偶に子供が騒ぐ声や親御さんの自転車の置き方にムッとすることがあります。
しかし、この話を伺い、少し見る目を変えることが出来ました。
機会があれば、お子さんに触れ「気」を感じてみたいと思います。
カテゴリー: スタッフブログ
Comments Off on 営業活動日記 「子供の『気』」
2016年08月22日営業活動日記 「お盆の手伝い」

皆様、こんにちは。井上久恵です。
前回の日記で、私の間抜けな夏休み前編をお送りしました。
今回は後編です。
実は、こっちをメインに書きたかったのですが、
私の中でもインパクトが大きい出来事だだったので、
順番が逆になりました。
なぜ後編をメインに書きたかったかというと、これをする為に帰省したからです。
それは、「お盆の手伝い」。
今年は暦上、お盆の最中ではなくお盆前から休みを頂いたので、
せっかくなら手伝いと勉強の為と思い早めに帰省しました。
島根のお盆は、13日が迎え盆で15日が送り盆です。
(※ちなみに、母方の鳥取では16日が送り盆です。田舎同士が県境に位置していますが、日にちが異なります)
12日には母と一緒にお盆に備え買出しと、仏間をキレイに整えました。
普段は穏やかで優しい祖母ですが、祖母にとってお盆は1年で1番の大イベント。
父にあれこれとテキパキ指示を出し、「これはこげすーだー(訳:これはこうするんだ)」
「おじいさんが帰ってくーけん、キレイにしちょかないけん!(訳:おじいさんが帰ってくるから、
キレイにしておかないとダメ!)」
「あーけ、こんなことしちょーなーとおじいさんがおこーなーで!
(あぁ、もう、こんなことしてるとおじいさんが怒るわ!)」と、時に声を荒げ、ピリピリしていました…。
私は盆ちょうちんを飾る係につき、そんな祖母の意外な一面を見つつ、黙々と作業をしていました。
幼い頃島根にあった盆ちょうちんは、確かクルクル回るキレイなものでした。
しかし、箱を開けてみると簡素なちょうちんに変わっていました。
ピリピリしている祖母にはとても声を掛けられなかったので、その理由をコソッと母に聞いてみると、
「(私を含め)こういうことをやる人たちは高齢化してるから、簡単に組み立てられるものの方が良い」とのこと。
なるほど、納得した気持ちと、こういう文化もいずれ無くなってしまうのか…?と危惧する気持ちがありました。
一家が協力したお陰で、スムーズに飾り付けは完了しました。
13日からは親戚やお客さんのおもてなしです。
しかし、これも昔と比べ大分簡素なものになりました。
昔は仕出しを頼んだり、客間に座布団を並べお酒を並べ、とにかくおもてなしに力を入れていました。
が、仕出しも座布団もお酒も無し。
母が言ったように、お客さんも高齢化が進み、立ったり座ったりがきつい和室には入らなくなりました。
食べたり飲んだりもしなくなったので、仕出しも無しになったそうです。
ただ一つ変わらないのは、一番最初にお客様にお出しする飲み物です。
それは「お抹茶」。
実家がある地域は、京都、金沢とならび日本三大和菓子処であり、
その昔松平藩がこの地域に、形式に捉われない茶道を広めたと言われています。
一家に1セット抹茶道具があるという噂も…。
このような地域説を去年初めて知り、私は大変驚きました。
なぜなら、我が家では抹茶を飲むことは日常だったからです。
母方の祖母は茶道の先生で、母も茶道を習っていました。
朝10時とお昼の3時は必ず抹茶を飲むことが当たり前だったのです。
私たち姉弟も(細かい作法はさておき)当然抹茶を点てられますし、前述の通り私たち兄弟もみな抹茶道具を
一式持っています。
ということで、お客さんが来た時の私は、一番茶である抹茶を点てる係になりました。
一度にバッと来られると私の手は悲鳴をあげます。
(※ちなみに2杯飲むのが慣わしです)
また「その茶碗は人間国宝の◯◯さんの茶碗だから気をつけて!!」と言われると、
逆に力が入りガタガタと緊張します。
しかし、美味しく点てられると褒めてもらえるのでやり甲斐もあります。
一通りお盆のイベントを終え、最後に両親から「とても助かった」と感謝して貰え、
祖母は「おじいちゃんも喜んでなーわ(訳:喜んでるわ)」と言ってもらえ一安心。
この忙しい時期、足手まといになるのは私としても御免ですから。
祖母の目が黒いうち、両親の為に今後も役に立てれば、
抹茶を含め「島根イズム」を絶やすことのないようにしていきたいと改めて思いました。
こうして私の夏休みは過ぎていったのでした。
カテゴリー: スタッフブログ
Comments Off on 営業活動日記 「お盆の手伝い」
2016年08月21日営業活動日記 「セルアージュ横濱関内エリーゼ」
.jpg)
皆様、こんにちは。西村友里です。
弊社の投資家様にご購入頂いた築浅の分譲マンションが空室となり、
入居者募集を開始致しました。
JR根岸線・横浜市営地下鉄ブルーライン「関内」駅から徒歩2分の好立地です。
平成24年築で共用廊下はホテルライクな内廊下となっております。
内廊下のメリットをご紹介させて頂きます。
①天候の影響を受けにくく、大雨や強風、寒い日でも快適に通行が出来る。
②外部からの視線が遮られるので、プライバシーの確保がしやすい。
③侵入経路が限られているため、外部からの不正侵入が抑えられ、防犯性が高い。
④カーペット敷きなので、足音が響きにくいため、静けさが保てる。
⑤空調が効いているので快適。
その他、建築の目線からいえば、風雨の影響を受けないため、デザインの幅・内装材の選択肢が広がり、
高級感を演出することが出来るというメリットもあるそうです。
マンションの近くには「CERTE(セルテ)」というショッピングモールがあり、
スーパー、靴・鍵屋、薬局、携帯ショップ、保険会社、はんこ屋、インターネットカフェ、
100円ショップ、内科、ギャラリー、ビューティークリニック、歯医者、本屋、フィットネスクラブ、
ホットヨガスタジオ、飲食店、ライブハウス等と様々なものが揃っておりますので生活に便利です。
【物件概要】
◇所 在 地: 横浜市中区万代町2丁目3-1
◇構 造: 鉄筋コンクリート造11階建 9階部分
◇間取・面積: 1LDK 40.29㎡(12.18坪) バルコニー面積5.44㎡
◇築 年 数: 平成24年1月
【賃貸条件】
◇賃 料: 155,000円
◇管 理 費: 10,000円
◇礼 金: 賃料の1ヶ月分
◇敷 金: 賃料の1ヶ月分
◇契約期間: 2年
◇更 新 料: 新賃料の1ヶ月分
【設 備】
オートロック、給湯、クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置場、ウォシュレット、
電話台、食器棚、システムキッチン、3口ガスコンロ、食器洗い乾燥機、浄水器、
TES式温水床暖房(LDK)、エアコン(LDK)、ミストサウナ付浴室換気乾燥機、都市ガス等
今週中にはクリーニングが終わる予定です。
是非現地をご覧頂ければと存じます。
ご興味がおありの方は、私西村までご連絡ください。
皆さまからのご連絡をお待ちしております。
カテゴリー: スタッフブログ
Comments Off on 営業活動日記 「セルアージュ横濱関内エリーゼ」
2016年08月20日営業活動日記 「旅にトラブルはつきものですが・・」

皆様、こんにちは。井上久恵です。
10日(水)から17日(水)まで夏季休暇を頂きました。
いつものように実家のある島根に帰省する予定だったのですが、
島根に向かう<ついで>に、久々に一人旅をしようと思い立ち、
どこか寄れるところはないかと考え、姫路城に行くことに決めました。
何を隠そう、私は「城好き」です。
城跡を含め日本各地の城という城を回らないと気が済みません。
以前「行きたい!」と思ったタイミングが、平成21年から始まった
姫路城天守保存修理工事中でしたので、ようやく敢行することができました。
西日本が連日猛暑であることはニュースや島根にいる両親から聞いて知っていました。
暑さから来る疲労を考慮して無理をせず姫路に1泊滞在し、姫路城見学だけに徹することにしました。
「姫路城を見に行く」と何人かに話をしていましたが、
口を揃えて「上まであがるの?(あがったの?)」と皆が聞いてきます。
「なぜだろう??」と不思議に思ったのですが、現地に赴きその理由が分かりました。
姫路城自体がとても大きなお城なので、敷地もその分とても広いのです。
姫路城の入口には、「この先坂が続きます。足元に気を付けてください。」と
書かれている看板が設置されているのを見て、その前でしばしフリーズ・・・。
私はヒールを履いていました。周りを見渡すと、他の参観者はスニーカーだったり底がない靴を履いています。
「しまった~ぁ!!」
何の情報も持たず、突発的に来てしまった為、姫路城がどのくらいの敷地面積を誇っているだとか
なだらかな坂をのぼった上に、さらに6階建ての建物(大阪城のようにエレベーターはありませんでした)が
そびえ立っていることなど、私はつゆ知らず。
足はガクガク、想像をはるかに超える暑さに体が堪えたのは言うまでもありません。
天守閣までのぼりましたが、敷地周辺散策をすることは諦めました。
一般的に、城内では「飲食禁止」となっておりますが、熱中症予防の観点から
「城内でも、水分を摂って頂きますようお願いします」と
普段とは逆に注意を促している場面に遭遇したのは初めてでした。
何度か一人旅をしていますが、旅にトラブルはつきものです。
最近はトラブルが起こっても、「これも一人旅の醍醐味よね」なんて図々しいことを考えるようになってきました。
今回もトラブルからの学びがいくつかありました。
1.真夏の旅はそろそろ控える(「若いから大丈夫!」が通用しなくなってきました)
2.炎天下、黒いパンツ(ズボン)は履かない(直射日光の熱を吸収し、下半身がビチョビチョになりました)
3.切符を失くさない
今回一番イタイ失敗が3でした。翌日、姫路から島根に向かう為の乗車券をこの日に紛失してしまいました。
往復乗車券(12日間有効)を購入すると、片道ずつ乗車券を買うより料金が割引されるので、
横浜-島根間の往復乗車券を買って準備していました。
これには注意が必要で、1日目姫路駅で降りた(途中下車した)際、
出てくる乗車券を自動改札から取って、自身で保管しておかなくてはいけません。
幼い頃からしょっちゅう切符を失くすので家族、友人、恋人がいつも私から切符を回収していました。
それを今回マンマとやってしまいました。(心の中では「あぁ、やっぱりな」という気持ちが正直あります)
しかも、姫路城城内にアナウンスが流れていたのを知っていて、それを無視をした私。
『管理事務所で、JRの切符をお預かりしています。お心当たりの方は管理事務所までお越しください』という
アナウンスを・・・。
「JRって一言で言われても、東日本か西日本か東海か九州か分からないじゃん」などとその時は屁理屈ばかり
考えていましたが、ホテルに戻って翌日の準備をしている時に紛失していることに気が付いたのです。
「あの切符は、私だったかもしれない・・・」と。
ちなみに、父親に往復乗車券の購入方法を聞いて準備していたのですが、
実家に戻ってから今に至るまでこの件は父には内緒です。
「バカかお前はー!いくつになっても・・・、ちぇっ、何やっているんだー!」と言われるのは目に見えているので。
最後に、この日の夜ホテルでくつろいでいる時に、じわじわと頭痛に襲われました。
後から気づいたのですが、どうやら軽い熱中症だったようです。
水分補給はまめに摂っていましたし、炎天下歩いたのは4時間ほどでしたが、
体は自分が思っている以上に正直に反応するんだなと気付きました。
まだまだ暑い日が続きます。皆様も季節柄、ご自愛ください。
カテゴリー: スタッフブログ
Comments Off on 営業活動日記 「旅にトラブルはつきものですが・・」
2016年08月19日営業活動日記 「満喫した夏季休暇」

皆様、こんにちは。西村友里です。
8月10日(水)~8月17日(水)まで、夏季休暇を頂きました。
いつもの夏なら、夏季休暇前半には岡山へ帰省する私ですが、
今回ばかりは帰っていられない事情がありました。
その事情とは、都内で大好きなバンドの新曲リリースパーティーがあり、
それに参加した為です。このバンドを知ってからまだ5ヶ月の私ですが、
バンドへの思い入れが強いためなのかはわかりませんが、
なぜかこのバンドに関することには、「幸運」が舞い込んできます。
たった5ヶ月の間に、新曲のエキストラに参加出来る抽選に当たったり、
ラジオで送ったメッセージを読んでもらえたり、そして今回はなんと「リリースパーティ」に当選して招待され、かつ席順のくじ引きで1番となり、最前列の席を選ぶことができました。嬉しいことの連続です。
弊社代表からは、「その運を仕事でも発揮してほしいのになあ・・・」と、ポツリつぶやかれてしまうほどです。
また、夏休み中はバンドを通じて仲良くなった友人と食事に行ったり、
大学時代の友人と姫路で会ったり、父と焼き肉を食べに行ったり、お墓参りをしたり、
家族で居酒屋に行ったり、高校時代の友人と会ったりと、思う存分夏休みを満喫してきました。
5年ぶりに幼馴染とも会うことができ、お家にお邪魔してまいりました。
幼馴染は今年の1月に出産し、子供にも会うことが出来ました。
喜びもつかの間、私の頭の中では幼馴染の記憶が20歳で止まっており、
時の過ぎ去る速さに、愕然としました。
余談ですが、弊社の朝礼で活用している一般社団法人倫理研究所が出版している
「職場の教養」には以下ようなことが書かれていました。
8月9日(火)帰郷のカウントダウン
九州出身のKさんは、一昨年4月に入社しました。
大学進学による上京以来、「お金がかかるから」と、帰省は4年間で1度だけでした。
そんなKさんですが、ある先輩の言葉をきっかけに、お盆と年末年始は必ず帰省するようになったのです。
先輩は次のように言いました。
「縁起の悪い質問かもしれないけれど、君の両親は何歳まで生きるだろうか。
仮にあと30年だとして、毎年1回帰省しても、30回しか両親に会えないことになる。 その中で、ゆっくり話ができるのは何回だろう?」
先輩の話を聞いたKさんは、〈親に会える時に会っておくことが、自分には必要だ〉と気がついたのでした。
「孝行したい時に親はなし」とは、昔からいわれることです。
後悔によって実感するよりは、後悔しないための指針として、この言葉を胸に刻みたいものです。
故郷を離れて働く人はもとより、親と同居している人も含めて、時には両親とゆっくり話をする時間を持つのもいいでしょう。
今日の心がけ「後悔する前に孝行しましょう」 ※職場の教養より
ここに書かれている親と会える回数があと数十回しかないことは、SNSで見たことがあり知っていました。
毎回甥っ子に会うために帰省しているように感じていましたが、実は一番親に会いたくて帰っていることに
今更ながら気付きました。
また、特に祖父母の方がより会える回数が限られていると思いますので、これからも必ず長期休暇の際は、
帰省するようにいたします。
年末に帰省する際は、妹に二人目の子供が誕生しておりますので、会えることを楽しみに、日々の業務に励んで参ります。
カテゴリー: スタッフブログ
Comments Off on 営業活動日記 「満喫した夏季休暇」
2016年08月18日営業活動日記 「お盆の行事」
.jpg)
皆様、こんにちは。山口幸夫です。
皆様は、今年のお盆休みはどのように過ごされましたでしょうか。
私は故郷の三重県に帰省しました。
親戚の方の初盆があったため、次女と共に行ってまいりました。
帰省中の8月11日、小学生の頃から大変お世話になった方が亡くなり、
8月15日にお通夜、16日に葬儀が行われました。
親戚の方々もどんどん高齢になるため、お盆に帰省する回数は年々増えています。
こればかりは仕方のないことです。
私の田舎では、地元のお寺に13日と15日に通って、いわゆる迎え盆と送り盆の行事が営まれます。
13日にお寺から提灯を預かり、15日にお返しする風習があります。
また、地元の小学校では14日、15日に盆踊りが行われます。
私が子供のころは13日から15日の3日間行われていました。
お盆の行事は、各地方で形式が異なりますので、この機会に調べてみました。
お盆とは、正式には【盂蘭盆(うらぼん)】といい、古代のインド語の一つであるサンスクリット語の
「ウランバナ」を漢字にあてはめて読まれた言葉です。
お釈迦様の弟子の目連は、母親が死後の世界で餓鬼道に堕ちて飢えに苦しんでいる姿を見て、
お釈迦様に母を救う方法の教えを請いました。
その教えに従って、布施や供養を僧侶や多くの方々に施したところ、
その功徳により母親は極楽浄土に行くことができました。
それ以来、目連が多くの人に施しをした7月15日は先祖供養の大切な日となったと伝えられています。
一方、中国では仏教以前から死者への祖霊の儀式もありました。
これらが一緒になって日本に祖霊信仰として伝わってきたとも言われています。
お盆の時期、お寺では「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という法要を執り行います。
各家庭ではお盆には故人の霊が帰って来るといわれ、お供えや提灯を飾ってお迎えします。
旧暦の頃(明治時代以前)のお盆は、7月15日を中心として13日に迎え火、16日に送り火を行なっていました。
新暦になると、お盆の期間が農作業の繁忙期と重なるため、ひと月遅れの8月13日から16日に
お盆をするところが多くなりました。
現在も地域によってお盆の時期はまちまちですが、大きく分けて7月13日から行う地域と、
8月13日から行う地域があるようです。
全国のお盆の行事の中で特徴的なものをご紹介します。
東北、宮城県では、8/16に“わら”で作った「盆舟」を流します。
盆舟の舵取りは新盆を迎えた人の霊が行うので、沖へ流れ出れば供養できたと喜びます。
昭和の中頃までは川に流していましたが、今はお寺に持ち寄るのが一般的なようです。
青森県大川原では、8/16の夜、「火流し」と呼ばれる行事が行われます。
アシガヤを編み上げた長さ3m弱・幅1.5m・帆柱3mの舟3隻に火をつけ、
1隻を5~6人づつの若者が引きながら川を下ります。
関西では通常のお盆とは別に、8/23から8/24にかけて、「地蔵盆」と呼ばれる子供たちが主役の行事があります。
準備は初日の朝に町内の人が協力して行い、地域で祀ってあるお地蔵様を綺麗に飾り付け、
お供えものや灯篭を置きます。
日中は僧侶の読経や子供へのおやつの配布があり、夜は踊りや花火など子供向けの催し物をして
賑やかに過ごすことが多いようです。
地域によっては、地蔵盆の朝、大きな数珠を囲んで座り、お経にあわせて順々に回す「数珠回し」が
行われるところもあります。
九州では綱引きが盛んです。
理由は諸説ありますが、目蓮尊者が母親を地獄の釜から引き上げたことに由来する、
綱引きの勝敗でその年を占うなどと言われています。
福岡県筑後市の熊野神社で8月14日に開かれる「久富盆綱引き」では、
全身にすすを塗って黒鬼に扮した子供たちが大綱を持って町内を引き回します。
長崎県では精霊流しが盛大に行われます。
このように全国には様々な形式のお盆の行事があるものです。
いずれにしても、その目的はご先祖様や亡くなった方が現世に戻ってくることに対する行事の中で、
自分が生まれるきっかけとなったご先祖様へ感謝の気持ちを持つということだと思います。
私も何とか無事にその目的を果たすことが出来ました。
行事の時だけに限らず、ご先祖様に対する感謝の気持ちをいつも忘れないようにして参ります。
カテゴリー: スタッフブログ
Comments Off on 営業活動日記 「お盆の行事」
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら