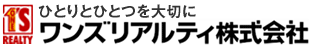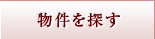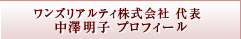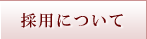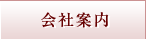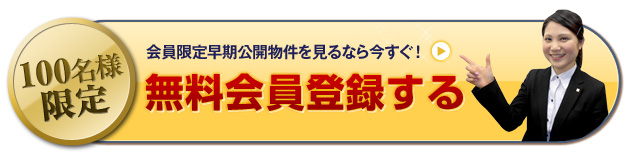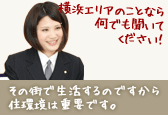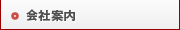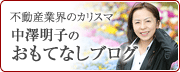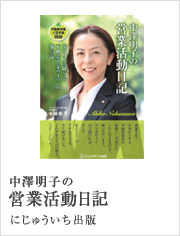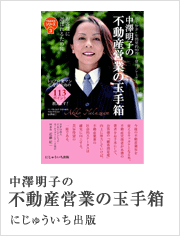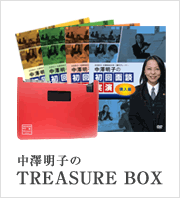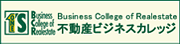.jpg)
皆様、こんにちは。山口幸夫です。
皆様は、今年のお盆休みはどのように過ごされましたでしょうか。
私は故郷の三重県に帰省しました。
親戚の方の初盆があったため、次女と共に行ってまいりました。
帰省中の8月11日、小学生の頃から大変お世話になった方が亡くなり、
8月15日にお通夜、16日に葬儀が行われました。
親戚の方々もどんどん高齢になるため、お盆に帰省する回数は年々増えています。
こればかりは仕方のないことです。
私の田舎では、地元のお寺に13日と15日に通って、いわゆる迎え盆と送り盆の行事が営まれます。
13日にお寺から提灯を預かり、15日にお返しする風習があります。
また、地元の小学校では14日、15日に盆踊りが行われます。
私が子供のころは13日から15日の3日間行われていました。
お盆の行事は、各地方で形式が異なりますので、この機会に調べてみました。
お盆とは、正式には【盂蘭盆(うらぼん)】といい、古代のインド語の一つであるサンスクリット語の
「ウランバナ」を漢字にあてはめて読まれた言葉です。
お釈迦様の弟子の目連は、母親が死後の世界で餓鬼道に堕ちて飢えに苦しんでいる姿を見て、
お釈迦様に母を救う方法の教えを請いました。
その教えに従って、布施や供養を僧侶や多くの方々に施したところ、
その功徳により母親は極楽浄土に行くことができました。
それ以来、目連が多くの人に施しをした7月15日は先祖供養の大切な日となったと伝えられています。
一方、中国では仏教以前から死者への祖霊の儀式もありました。
これらが一緒になって日本に祖霊信仰として伝わってきたとも言われています。
お盆の時期、お寺では「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という法要を執り行います。
各家庭ではお盆には故人の霊が帰って来るといわれ、お供えや提灯を飾ってお迎えします。
旧暦の頃(明治時代以前)のお盆は、7月15日を中心として13日に迎え火、16日に送り火を行なっていました。
新暦になると、お盆の期間が農作業の繁忙期と重なるため、ひと月遅れの8月13日から16日に
お盆をするところが多くなりました。
現在も地域によってお盆の時期はまちまちですが、大きく分けて7月13日から行う地域と、
8月13日から行う地域があるようです。
全国のお盆の行事の中で特徴的なものをご紹介します。
東北、宮城県では、8/16に“わら”で作った「盆舟」を流します。
盆舟の舵取りは新盆を迎えた人の霊が行うので、沖へ流れ出れば供養できたと喜びます。
昭和の中頃までは川に流していましたが、今はお寺に持ち寄るのが一般的なようです。
青森県大川原では、8/16の夜、「火流し」と呼ばれる行事が行われます。
アシガヤを編み上げた長さ3m弱・幅1.5m・帆柱3mの舟3隻に火をつけ、
1隻を5~6人づつの若者が引きながら川を下ります。
関西では通常のお盆とは別に、8/23から8/24にかけて、「地蔵盆」と呼ばれる子供たちが主役の行事があります。
準備は初日の朝に町内の人が協力して行い、地域で祀ってあるお地蔵様を綺麗に飾り付け、
お供えものや灯篭を置きます。
日中は僧侶の読経や子供へのおやつの配布があり、夜は踊りや花火など子供向けの催し物をして
賑やかに過ごすことが多いようです。
地域によっては、地蔵盆の朝、大きな数珠を囲んで座り、お経にあわせて順々に回す「数珠回し」が
行われるところもあります。
九州では綱引きが盛んです。
理由は諸説ありますが、目蓮尊者が母親を地獄の釜から引き上げたことに由来する、
綱引きの勝敗でその年を占うなどと言われています。
福岡県筑後市の熊野神社で8月14日に開かれる「久富盆綱引き」では、
全身にすすを塗って黒鬼に扮した子供たちが大綱を持って町内を引き回します。
長崎県では精霊流しが盛大に行われます。
このように全国には様々な形式のお盆の行事があるものです。
いずれにしても、その目的はご先祖様や亡くなった方が現世に戻ってくることに対する行事の中で、
自分が生まれるきっかけとなったご先祖様へ感謝の気持ちを持つということだと思います。
私も何とか無事にその目的を果たすことが出来ました。
行事の時だけに限らず、ご先祖様に対する感謝の気持ちをいつも忘れないようにして参ります。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら