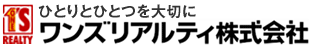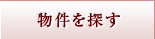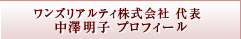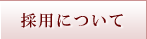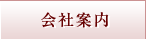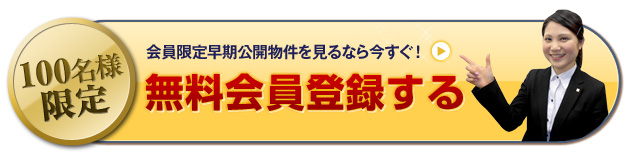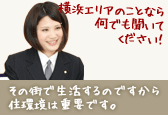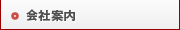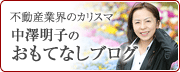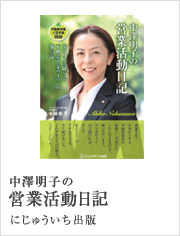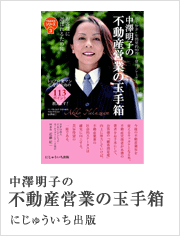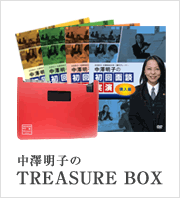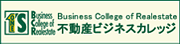皆様、こんにちは。中澤明子です。
今日の玉手箱「宅地建物取引士の誕生」
ご存知の通り、不動産業界もようやく弁護士や会計士など専門資格の職業を意味する、
「士業」の仲間入りを果たしました。
お客様の大切な財産を管理する仕事なのに、「なぜこんなに遅かったのか」というのが、
私の中での疑問点ではありますが、名称が変わったことにより「志を高くもった業界人」が
増えることを期待したいと思います。
「宅地建物取引士」が誕生したといっても、まったく新しい国家資格が誕生したわけではありません。
不動産流通の円滑化を目的に制定された宅地建物取引業法を改正し、これまでの「宅地建物取引主任者」を
改称したわけですが、「取引主任者」と「取引士」では大きな違いがあることを、私たち不動産業に携わる者は
意識をし業務に臨まなければなりません。
◇「重要事項説明」の不実告知
不動産業界では、紛争相談の3割が「重要事項説明」の不実告知にあると言われています。
もちろん、人が調査を行うのですから、調査する人の能力や質問の仕方、物の見方等により、
調査ミスや調査漏れなどが発生するのは仕方がないことだと考える人がいるかもしれませんが、
プロとして決して許されることではありません。
売買仲介の場合、不動産会社と売主様との連携が重要な業務のひとつです。
例えば、役所調査だけではわからないことでも、所有者である売主様がわかっていることや、
保管している資料や情報などがあります。
これらのことも重要事項に反映させるのが私たちの役割です。
遡ること、宅地建物取引主任者の名称が初めて法律に盛り込まれたのは1964年です。
そして1971年に取引主任者による購入物件に関する重要事項説明と契約締結時の書面交付が義務づけられました。
1980年に、維持向上を図ることを目的とした、法定講習制度が創設され、5年に一度の免許更新時に、
講習で改正法令や紛争事例などの最新情報を学ぶことが定められました。
しかし、実際には5年に一度の法定講習は長すぎます。
中には法定講習を面倒くさいとか必要性がないものと判断している宅建業務の従事者もいるようですが、
これはもう問題外です。
法律や税制などは毎年何かしらの変化があります。
もちろん、プロですから法定講習に頼らずとも、日常アンテナを張って、努力を積み重ねて
勉強するのが当たり前です。
重要事項説明に関するトラブルが多発していることを考えると、プロとして仕事にプライドと誇りを持って
一般消費者のために臨んでいるのではないことが理由のひとつではないかと思います。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら