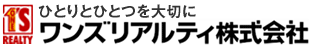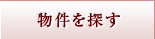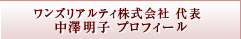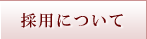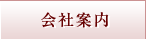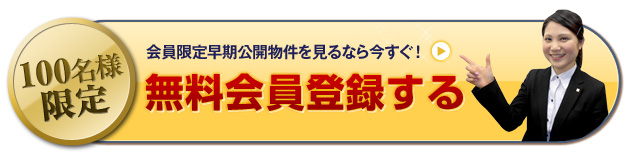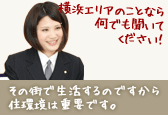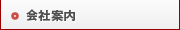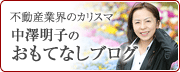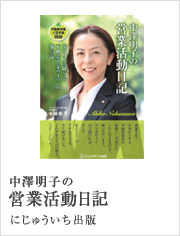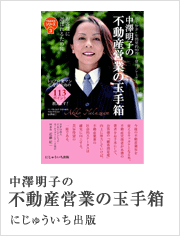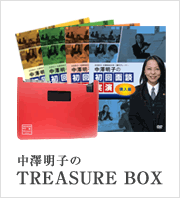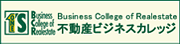皆様、こんにちは。西村友里です。
先日、セミナーの補助を行うため、代表の大阪出張に同行させて頂きました。
セミナーは、大勢の皆様にお集まり頂き、大盛況に終わりました。
その後、代表のリクエストにより、京都に1泊して帰ることになりました。
紅葉にはまだ早く、台風の影響で雨が降ったり止んだりのお天気でしたが、
さすが京都です。雨が似合う情緒あふれる景色を思いっきり堪能することが出来ました。
私が京都で一番好きな神社の「伏見稲荷」を始めとし、三十三間堂、清水寺、八坂神社、
源光庵など有名な観光名所を巡って参りました。
驚いたのは、平日であいにくのお天気にも関わらず、京都のどこに行っても、
日本人よりも外国人観光客のほうが多いのでは・・と思うほど、
外国人観光客であふれていたことでした。
歴史あるお寺巡りは、神聖な場所で身も心も清めることができ、パワーがみなぎった気がします。
また、初めて訪れた「先斗町(ぽんとちょう)」は、情緒あふれる素敵な街並みに感激し、
是非またゆっくり訪れたいと思いました。
先斗とは、
三条通の一筋南から四条通まで通じる鴨川に沿った南北500mあまりにわたる
細長い通りのことを指し、京都における著名な花街の一つです。
この地に水茶屋が初めて設けられたのは、正徳二年(1712)の頃といわれ、
初めは高瀬川を上り下りする、高瀬舟の船頭や旅客目当ての旅籠屋が茶立女を置いていました。
安政6年(1859年)になって芸者嫁業の公許が下り、祇園と並ぶ花街として有名になりました。
べにがら格子の家が両側に建ちならんでおり、東西に五十番まで数える大小の路地があります。
幕末に勤皇と佐幕に分かれて抗争した志士たちが、追われてこの露地に身を潜めたり
待ち伏せしたりしたそうです。
先斗町の語源については、東が鴨川(皮)、西が高瀬川(皮)、皮と皮にはさまれた鼓を叩くと
ポンと音がするのをモジって、ポント町の名が生まれたとも、ポルトガル語のPONT(点、先端の意味)から
きているとも言われています。
街が河口にむかって突出する形、洲崎のような場所に形成されたので、
そのように呼ばれるようになったのではないかという説です。
かつて日本にはじめて来たヨーロッパ人といわれる本家のポルトガル人宣教師達によって伝えられたものです。
先斗町は、処狭しと数多く建ち並ぶ飲食店が有名ですが、中でも私が気になったお店は、「柚子元」というお店です。柚子を使った料理がメインで、カウンター席しかないこじんまりとしたお店ですが、この日は満員御礼で入れませんでした。
このお店の柚子餃子を食べてみたかったのですが・・・残念。また次の機会においでやすということだと気持ちを切り替え、
別のお店で美味しい「すき焼き」をお腹いっぱい頂き、大満足だったことは言うまでもありません。
京都には修学旅行や家族旅行、友人が京都に住んでいたこともあり、何度か訪れたことがありますが、
まだまだ知らない場所が数多くあり、その度に新しい魅力を発見できる街だから大好きです。
是非また訪れたいと思います。
楽しいひと時を有難うございました。
余談ですが、黄色の新幹線「ドクターイエロー」を遂に見ることが出来ました!
大阪に向かう新幹線を新横浜駅で待っているときに、颯爽と現れて、ものの数分で去っていきました。
胴体しか写真に納めることは出来ませんでしたが、生で見ることが出来てとても嬉しかったです。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら