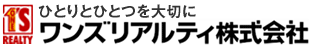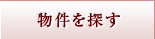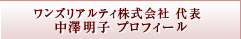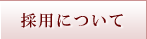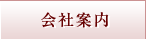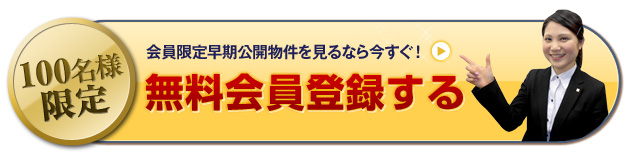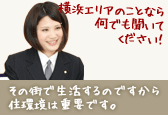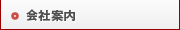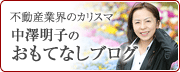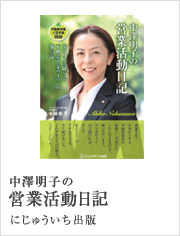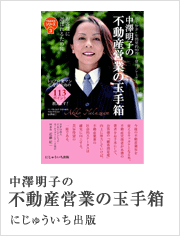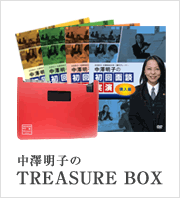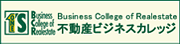皆様、こんにちは。西村友里です。
8日(金)の夜、倫理法人会主催の「倫理経営講演会」に、
社員全員参加させて頂きました。
弊社の代表は常に「学び」を大切に考えており、経営者の会にも
社員を同席させて勉強する意識付をしています。
講演会は二部構成となっており、第一部は「朝礼実演」でした。
株式会社中込製作所様が毎朝行っている朝礼を披露してくださいました。
代表取締役 日向亮司氏は、横浜市倫理法人会の副会長でもあられます。
100名いらっしゃる社員さんの中から、この日は社長はじめ30名のスタッフが舞台に立ち
活気あふれる朝礼を実演して下さいました。
合言葉は「目指せ!朝礼日本一!」をモットーに、2年ほど前から『活力朝礼』を行っているそうです。
『活力朝礼』とは、一日を元気よくスタートさせるためのものです。
中込製作所の皆さんの滑舌の良い大きな声と機敏な動きは、観ている側も元気が出ました。
活力朝礼を導入している企業では、社内の雰囲気や社員の考え方や行いが、導入前と比べて
良い結果を生み出しているそうです。
弊社でも毎朝朝礼を行い、お客様視点での物の見方や考え方、社員間の情報の共有化に力を入れております。
『活力朝礼』の目的は以下4つです。(愛媛県倫理法人会HPより)
①スタートを合わせる(方針の徹底)
②モチベーションを高める(士気の高揚)
③コミュニケーションを深める(チームワークの向上)
④マナーを磨く(基本動作の習慣)
中込社長も「今まで取引先の方が物販を持って来ても「そこに置いといてください」とだけ言って、
目も合わさない従業員が多かったが、活力朝礼を取り入れてから、元気に挨拶をするようになり、
会社全体が明るくなった。」とおっしゃっておりました。
私も負けないように、朝から元気に取り組んで参ります。
第二部は、(一社)倫理研究所法人局普及事業部 次席 東海・北陸方面方面長
教育制度拡充担当 三浦 貴史講師による講演、「岐路に立つ~いま、求められる経営者の気骨~」でした。
講演時間である1時間、どれも大変勉強になるお話をしてくださいましたが、
全部書くと長くなりすぎるため、私が一番興味深かったお話をさせて頂きます。
気骨を養う為の岐路は、全部で3つあると伺いました。
まず初めに、このセミナーで初めて「気骨」(きこつ)という言葉を知りました。
意味は、「自分の信ずることを貫こうとし、容易に人に屈服しない、強い心。」です。(Google辞書より)
一つ目は、気骨を鍛える、養うためには、日常の小さなことから磨き高めていくこと。
小さなことにも「関心」を持つことが大切である。「愛」の対義語は「無関心」ですが、
「無」をとると、相手に「関心」を持てます。
小さな事には「威力」があり、ハインリッヒの法則のとおり、小さなことをついていくと大きなトラブルにならない。
常にチェック、チェック、チェックが大事だということをおっしゃっていました。
よく「第一印象で勝負が決まる」と言いますが、第一印象は短くて0.5秒、長くて6秒で決まるそうです。
たったその数秒で相手は自分に対するイメージを持つため、見た目だけでなく、礼儀、笑顔、声の大きさの
全てが大切になります。
また、「人間は自覚したときに変わるので、相手が自分に対して何を言っても変わりません。
中込製作所様にとって、その自覚の場が朝礼でした。」と先生はおっしゃっておりました。
こちらが何を言っても、本人が変わろうとする気持ちがないと無理だということは、
弊社代表や会長も常々おっしゃられていることです。
二つ目は、自分自身を良くしていくためにはどうすべきか。
「主役は誰か」を考えたとき、「自分が主役」になることが大切であるとおっしゃっていました。
どこの会社にも多かれ少なかれ、トラブルメーカーがいるかもしれません。
しかし、先生いわく「わが社の問題社員」といえば、問題社員の人だけを指しますが、
区切るところを変えるだけで、会社全体の問題になると話し、「わが社の問題。社員」
この言葉の違いは大きく、経営者自身が会社全体を見直すべきであることがわかります。
また、大きな力を出すポイントは、「声」を出すことであるとのことです。
普段は何も考えずに声を出していますが、意識して出すことにより、一層力が出てくるのだそうです。
綱引きを例に出していましたが、綱引きをしたとき声を出して応援すると参加している人は
手抜きをせずに綱を引くし、自らも声を出すことによって力が出るとおっしゃっていました。
言われてみると、柔道の試合でも試合開始の合図とともに選手は気合を入れるために大きな声を発します。
中学生の時に部活動で柔道を習っておりましたが、その時にも私は大きな声を出していませんでした。
それが大人になった今でも変わっておらず、代表や先輩に指摘されても一向に直すことが出来ません。
自覚が足りないのだと思います。直して参ります。
常に主役である「自分」が積極的に挨拶をすれば、相手も挨拶をするようになる。
自分が主役なのですから、自らを律して取り組むことが大切だと教わりました。
三つ目は、家庭の在り方を見直すこと
気骨を磨く場は家庭である。家庭の経営が仕事を支えるそうで、家庭内が上手くいっていないと
仕事も上手くいかない。家庭を良くするには、夫婦仲を良くすることが大事で、そのためには挨拶が大事である
とのことでした。実際に試しでやった方は、徐々に夫婦仲が良くなってきたそうです。
この三つ目に関しては、私はまだ未経験ですが、一つ目と二つ目は気を付けて参ります。
貴重な講演に参加させて頂きまして、大変嬉しく思います。有難うございました。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら