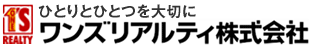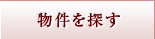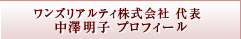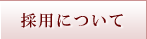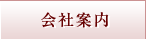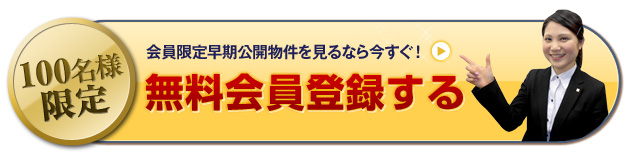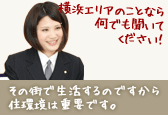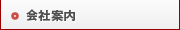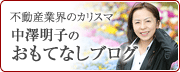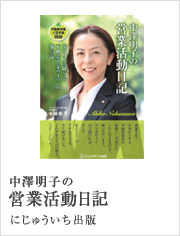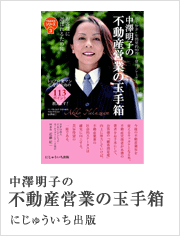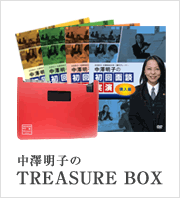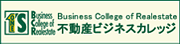皆様、こんにちは。西村友里です。
弊社の朝礼で活用している『職場の教養』(出版:一般社団法人 倫理研究所)には、
「今日の心がけ」などの毎日違うテーマと内容が書かれています。
また、この冊子の後ろのページには、「野生の教養」という欄があり、
南正人氏という方がコラムを書いています。
私はこの方のコラムを読むのを楽しみにしています。
今月のコラムもとても興味深い話でしたので、ご紹介させて頂きます。
『蜜と花粉をめぐる“駆け引き”』
色とりどりの花を楽しめる季節となりました。
さて、花は私たちを楽しませるために咲いているのでしょうか?
花は、自分のために咲いているのです。
動けない植物は、花粉の受け渡しや種子のばらまきを、多くの場合、動物や風などに頼っています。
花をもつ植物の多くは、蜜を出して昆虫を引きつけ、花粉を運んでもらいます。
きれいな花は、「ここに蜜があるよ」という広告塔なのです。
花にとって、蜜をたくさん出すことは、エネルギーの浪費でもあります。
できれば蜜を減らして、そのエネルギーを生長や種子の生産に回したいのです。
いっぽう昆虫は、蜜をもらう代わりに花粉を運ぶ約束をしたわけではありません。
昆虫は、蜜さえもらえればよいのです。
そこで、花粉を運んでほしい花と、蜜がほしい昆虫の駆け引きが始まるのです。
多くの花にとって、蝶は困った存在です。
長くて細い脚を使って花にとまり、長いストローを伸ばして蜜を吸っていくので、
蝶に花粉を付けることができません。
例外は、ヤマユリなどの大型のユリで、花の外側におしべやめしべを長く伸ばすことで、
蝶の羽の部分に花粉を付ける構造になっています。
蝶のように蜜だけを吸う昆虫を避けるために、筒型の花が進化しました。
筒の奥で蜜を出して、昆虫が花の中を進むうちに花粉を体に付けようという作戦です。
ホタルブクロという下向きに咲く筒状の花は、花びらの内側に毛をたくさん付けて登り難くしています。
小さな昆虫は、花の中心にあるおしべやめしべの花粉を付けて、蜜のある場所まで登らざるを得なくなります。
マルハナバチのように力のある昆虫は、花びらの内側を登りますが、その際に背中に花粉が付くのです。
ところが、昆虫の中には、そのような花の作戦を打ち破って蜜を強奪するものもいます。
花の蜜がある部分を外から噛み破って、蜜を吸ってしまうのです。
花と昆虫の駆け引きは今も続いています。
◆花と昆虫の心がけ◆
利己的と言われてもしたたかに生き抜きましょう
まるで花VS昆虫のような内容でとても面白かったです。
生き物は、元々自分の利益に向けて行動するという性質を持っているそうですが、
まさにそれを表していると思います。
ただ何気なく花を見ていたときとは、また少し違った見方をすることが出来るようになりました。
今後も「職場の教養」だけでなく、「野生の教養」も身に付けて参ります。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら