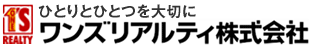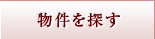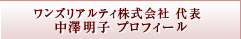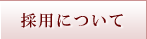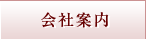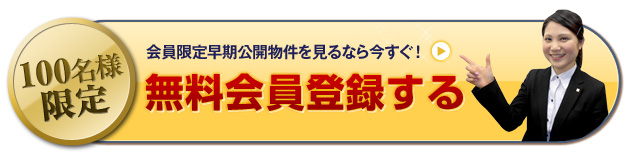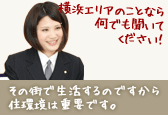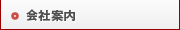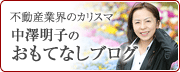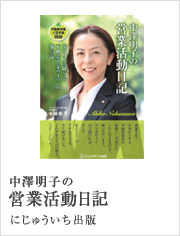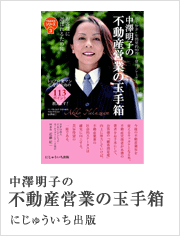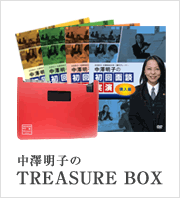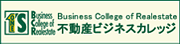皆様、こんにちは。山口幸夫です。
去る8月2日(火)に、神奈川新聞主催の「第31回神奈川新聞花火大会」が
開催され、例年通り弊社日本大通店では、第5回目となる花火観賞会が
行われました。
毎年、お世話になったお客様、賃貸管理物件のオーナー様をお招きして
おりますが、今年は新しいお客様も増えて、賑やかな観賞会となりました。
3年前に鶴見のアパートをご購入頂いたお客様は、普段のお仕事が大変忙しいため、
昨年まではご参加頂けませんでした。しかし、仕事も少し落ち着いたとのことで、
今年はご参加頂くことが出来ました。このお客様は、花火観賞をするのは数十年ぶりだそうで、とても感動されておりました。
夏の風物詩である横浜港の花火は、きっと皆様の心に残り、良き思い出となったことでしょう。
日本では、年に約8500 件の花火大会や花火ショーが行われています。
1日あたり20 回以上も日本のどこかで花火が上がっている計算になります。
日本の打ち上げ花火は世界一の技術を誇っているそうです。
私たちを魅了する花火の歴史について調べてみました。日本で打ち上げ花火が盛んになったきっかけは、1733 年に始まった両国花火です。
東京都の大川(現在の隅田川)に架かる、両国橋あたりで上げられていました。
これは現在に至るまで行われており、皆さんご存じの「隅田川花火大会」として今に続いております。
両国花火は、徳川吉宗がその前年の1732年に発生した、享保の大飢饉やコレラの大流行による
死者の弔いと悪霊退散の意味を込めて、花火を打ち上げたそうです。
5月末から8月まで、毎晩のように打ち上げられた花火は、民衆にとって世の中への不満と疫病の恐怖を
ひと時忘れさせてくれる楽しみとなっていたようです。
やがて、その打ち上げ時季から夏の夜空を彩る風物詩として定着していきました。
ちなみに、現代でも耳にする「たまや~」の掛け声は、両国花火を上げていた花火業者の「玉屋」を称えて
民衆が歓声を上げていたことに由来するそうです。
花火についてもうひとつ、いかにも日本らしい話があります。
海外の花火というのは、一方向から見ることを想定していた名残があり、
今でも円筒状の平面的な花火が作られています。これは、特に欧米において、館や建物の裏などから王族や貴族が楽しむためにのみ
花火を打ち上げることが多かった背景があり、一方向から見えるものであったそうです。
対して日本では先ほど述べた通り、時の将軍、徳川吉宗が民衆の楽しみのために
花火を打ち上げた歴史もあり、花火を見ることそのものに重点を置いており、
民衆があらゆる方向から楽しむことを可能にするために、花火を球状にして立体的に
打ち上げるようにしていたそうです。
こんな歴史からも、日本人がどうしてこれほど花火が好きなのか充分に理解が出来ます。
世界に目を向けるとテロなど傷ましい事件がたくさん起きています。
大盛況のまま無事に終わった横浜港の花火が、鎮魂とこれからの世界の平和につながるものに
なってくれるように心から願うばかりです。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら