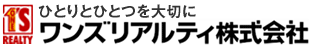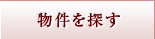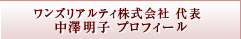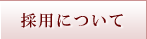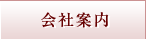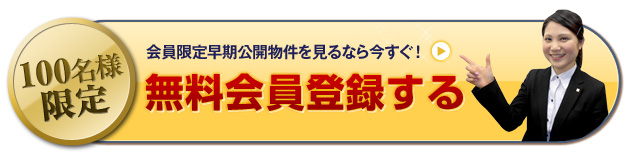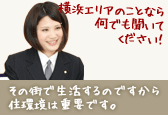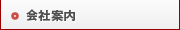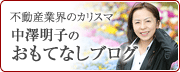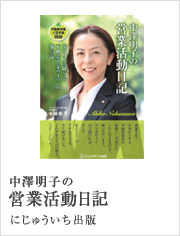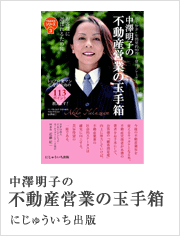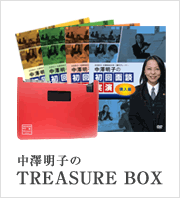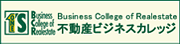皆様、こんにちは。西村友里です。
先日の「職場の教養」に記載されていた内容をきっかけに、今まで気にしたこともなかった「不動産会社」のルーツについて調べてみました。
「職場の教養」とは、弊社の朝礼で使用している「一般社団法人倫理研究所」が
発行している冊子です。
「不動産」という言葉そのものが登場したのは、明治初期だそうです。
明治になると憲法にも「不動産」という言葉が使われるようになり、
多くの不動産業者が誕生しました。
それまでは「不動産」ではなく、あくまでもただの「土地」という概念だったそうで、不動産の歴史とは「土地」の歴史であることを初めて知った私です。
日本における土地の歴史の始まりは、西暦300~500年です。
当時の豪族や貴族が土地を「縄張り」として捉えたことから始まります。
645年、中大兄皇子が蘇我氏を倒し、天皇を中心とした国作り(大化の改新)を進めたことにより、
土地は「公地」となりました。
743年、墾田永年私財法が定められ、土地の「私有」が認められるようになり、 この頃から土地を活用するという考えが生まれ始めました。
1580年、豊臣秀吉が太閤検地を行い、荘園(地方にあるまとまった私有地)が消滅し、
土地は大名が管理することになりました。
1603年、徳川家康が幕藩体制を築きまして、乱世が終焉し、商業が発展しました。 これにより、都市部に人口が集中し、長屋(賃貸住居)ができました。
これが不動産業の誕生と言われているそうです。(参照:「じつはおもしろい不動産の歴史!」)
明治中期になる頃には、現在のスタイル同様に物件を仲介する業者も誕生し、
不動産業としての幅も広がりました。
戦後の復興として一役買ったのがマンション事業で、戦争で焼け野原になった東京には、
住む家さえも無いという人々が溢れかえっていました。
そこで、復興の第一弾として掲げられたのが、住宅の確保です。
政府は銀行などの民間企業だけに頼るのではなく、自ら住宅融資を行う公的機関を
設立することを決定しました。この公的機関が住宅金融公庫や住宅公団です。
これらの公的機関設立がきっかけとなり、莫大な費用がかかるマンションの設立が
急激に加速することになったそうです。
学生時代に歴史の授業で学んだことがあるため、何となくこうだろうなという頭はありましたが、
実際に詳しい内容を知ることにより、不動産の深さをより一層感じることが出来ました。
すべてにおいて「学び」は大切です。今後も疑問に思ったことはすぐに調べ、自分の知識を蓄えたいと思います。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら