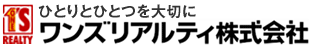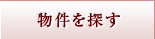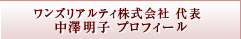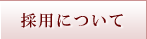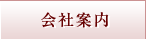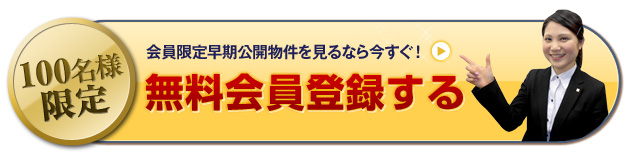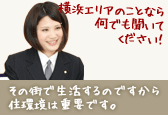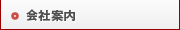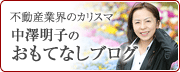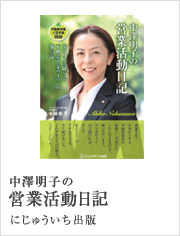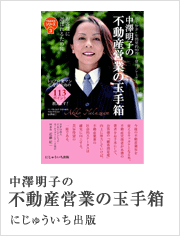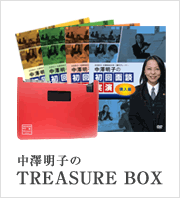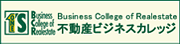皆様、こんにちは。西村友里です。
今年の七夕は、2017年7月7日と“7”が3つ揃った
ラッキーセブンデーでした。
皆さんにおかれましては、何か良い出来事が
起こりましたでしょうか。
私は、まさにラッキーデーでした。
新規のお客様からお問合せを頂き、ご案内のアポイントが取れたり、
管理物件にお住まいのお客様からご購入のごお話を頂いたりと、
仕事においての良いお話がいくつも舞い込んできました。
今年の七夕はお天気に恵まれたので、彦星と織姫は1年ぶりに会い、
話に花が咲き、楽しいひと時を過ごせたことと思います。
私は、2年前の日記に七夕の由来を書きました。
今年は「なぜ七夕に願い事をするのか」について調べてみたので、
お伝えします。
『七夕』という行事は、アジア圏で主に行われており、笹に願い事を書いた短冊を飾る風習は、
日本でしか行われていないそうです。
奈良時代に中国から日本に伝わり、庶民の間では広まらず、宮中の年中行事として催されていました。
お供え物をして、牽牛星(和名:彦星)・織女星(和名:織姫)を眺めたり、詩歌管弦の遊びをしていたそうです。
江戸時代に幕府が七夕を五節句の一つと定めたことにより、民間行事となり、
当時庶民の間で広まっていた習字の上達等、芸事上達の願いを短冊に書き、
笹竹に飾る風習が広がりました。
それが現在では、芸事に限らず色々な願いを書くように変わっていったということでした。
また、なぜ笹竹に願い事を飾るかについては、竹は冬の寒さにも負けず、真っ直ぐ育つ生命力が
備わっていることから、昔から神聖な力が宿っていると信じられていたそうです。
その為、あらゆる神事に使われていました。
また、竹には空洞があり、そこに神が宿っているとも言われているそうです。
このように神聖視されていた竹だからこそ、願い事を飾るのに用いられてきたというお話です。
古くから伝わる日本の伝統行事をこれからも大切にしていきたいと思いました。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら