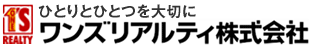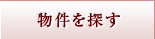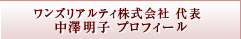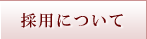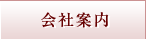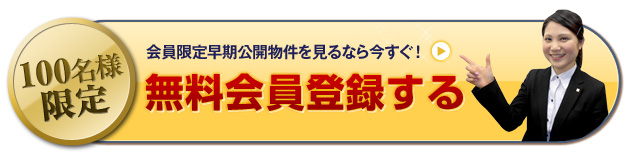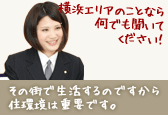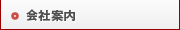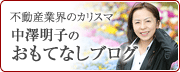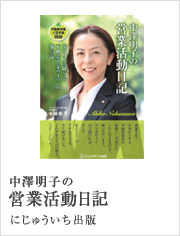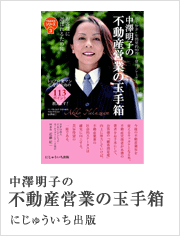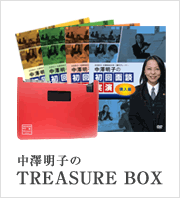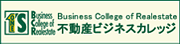.jpg)
皆様、こんにちは。西村友里です。
毎年横浜港にて開催されておりました、神奈川新聞主催の花火大会が、
今年から休止となりました。
毎年楽しみにしておりましたので、非常に残念で仕方がありません。
弊社の日本大通店からは、花火を一望することが出来ましたので、
毎年花火大会の日に合わせて、その年にお世話になった方々を日本大通店にご招待し、
花火観賞パーティーを開催しておりました。
今年は弊社代表からのご厚意により、神奈川新聞花火大会と比べると小規模ではありますが、
弊社のすぐ近くで行われる、もう一つの花火大会「横浜スパークリングトワイライト」に連れて行って頂きました。
スタッフが場所取りを頑張ったため、花火を真正面に見ることが出来ました。
おにぎりやお菓子を食べながら、美しい花火を観賞し、とても有意義な時間を過ごすことができました。
花火だけでなく、イルミネーションで飾られた船が山下公園前の海上を彩り、
ベイブリッジや氷川丸、マリンタワーもライトアップされていたので、とても綺麗でした。
夏のイベントを満喫出来て、とても良かったです。
先日、JRの電車に乗っていた際、ドアの上部にあるモニターに
「なぜ花火は夏に打ち上げるのか」という記事がありました。
その理由には、江戸時代に病気や飢饉などで多数の死者が出ていた時、
当時の将軍の徳川吉宗が隅田川の水神祭で花火を披露し、死者の御霊を慰め
悪疫退散を祈ったのが始まりとの説明が書かれていました。
花火のルーツは、一般的には中国で硝石が発見され、それを利用した狼煙が作られたことだとされています。
のろしとして通信手段として使われた火薬は、武器に使用され、花火の原型の一つである爆竹のようなものが
12世紀中頃に作られました。
硝石はシルクロードを経て中国からヨーロッパにも伝わり、ヨーロッパでも戦い道具として使われました。
観賞用の花火としては、14世紀後半のイタリア・フィレンツェで、キリスト教の祝祭などに使用されたのが始まりで、
ヨーロッパ中に広まっていきました。
そして大航海時代には、火薬や花火は世界各地へと広がりを見せました。
日本は、1543年ポルトガル人が種子島に鉄砲を伝えたことから始まります。
初めは鉄砲や狼煙として使用し、鑑賞・娯楽用の花火はそれより少し後の1613年イギリス人が
徳川家康のために披露したことから始まりました。
江戸時代になると花火師や花火売りなどが登場し、どんどんと改良されていったそうです。
1733年に行われた隅田川花火大会の起源となったこのときの行事に花火師を務めたのが
「玉屋」と「鍵屋」でした。
花火をあげた時に「たまやー」「かぎやー」とかけ声を掛けますが、こちらの花火師の名前であるとのことです。
鍵屋は江戸幕府御用達の花火商として成長し続けていき、8代目のとき、清七という優秀な番頭があらわれ、
のれん分けを許されて玉屋となったそうです。
江戸以外にも日本各地に花火は広がり、そして、先祖供養の意味合いやお祭り等で打ち上げられるようになり、
現在に至ります。 (参考:http://zatugaku1128.com/hanabi/)
今では、花火は見て楽しむイベントとして定着していますが、中国から来た火薬が日本でお盆や供養に使われ、
広がっていったようです。
夏はまだまだ始まったばかりですので、思いっきり働いて、夏季休暇を思いっきり楽しみたいと思います。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら