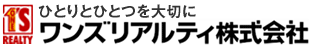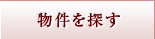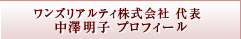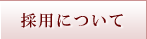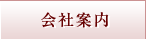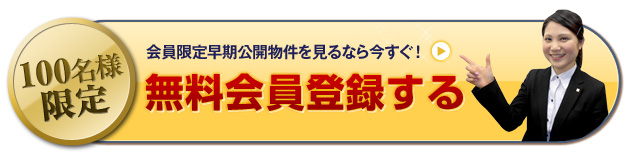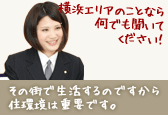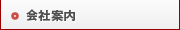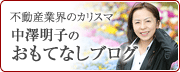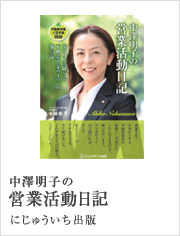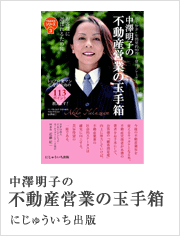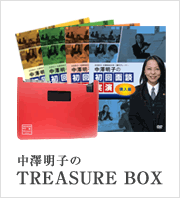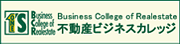.jpg)
皆様、こんにちは。西村友里です。
今日は7月7日、七夕です。
有り難いことに、2件のご契約を頂きました。
ひとつは戸建、ひとつは店舗です。
ご契約のおかげで私の心は晴れていますが、せっかくの「七夕」なのに外は雨降りです。
そこで今日は「七夕」の語源について調べてみました。
七夕の語源はいくつかあるそうです。
①精霊棚とその幡を安置するのが7日の夕方であることから、
7日の夕で「七夕」と書き、「たなばた」と発音するようになった。
②元来、中国での行事であったものが奈良時代に伝わり、
元からあった日本の棚機津女(たなばたつめ)の伝説と合わさって生まれた言葉。
③牽牛(彦星)と織女(織り姫)の二星が、それぞれ耕作および蚕織をつかさどるため、
それらにちなんだ種物(たなつもの)・機物(はたつもの)という語から「たなばた」となった。
六朝・梁代の殷芸(いんうん)が著した小説には、
『天の河の東に織女有り、天帝の子なり。
年々に機を動かす労役につき、雲錦の天衣を織り、容貌を整える暇なし。
天帝その独居を憐れみて、河西の牽牛郎に嫁すことを許す。
嫁してのち機織りを廃すれば、天帝怒りて、河東に帰る命をくだし、一年一度会うことを許す』
という一節があります。
これが現在知られている七夕のストーリーとほぼ同じ型となった、最も古い時期を考証できる史料のひとつと
なっているそうです。
また、「平家物語」によれば、貴族の邸では願い事をカジの葉に書いたと記されております。
二星会合(彦星と織り姫が会うこと)や詩歌・裁縫・染織などの技芸上達が願われたそうです。
江戸時代には手習い事の願掛けとして、一般庶民にも広がり、現代もこの風習が続いています。
日本3大七夕まつりと言えば、仙台市(宮城県) 、平塚市(神奈川県) 、安城市(愛知県)です。
仙台市8月6日(木)~8日(土)
平塚市7月3日(金)~5日(日)※開催終了
安城市8月7日(金)~9日(日)
古くからの風習を今後も大切にし、語り継いで頂きたいと思います。
皆様も是非七夕祭りに足を運んでみてはいかがでしょうか。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら