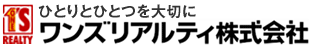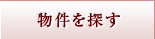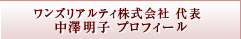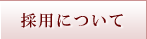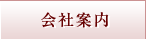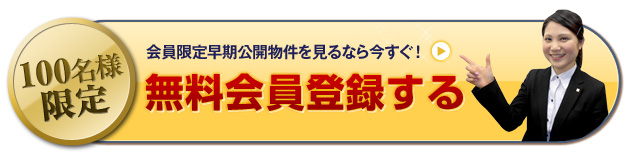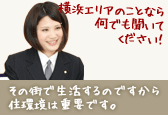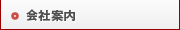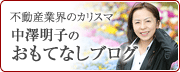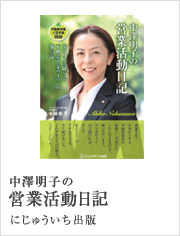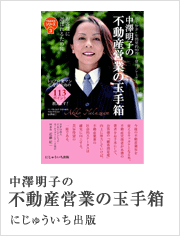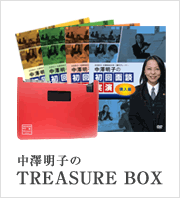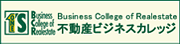.png)
皆様、こんにちは。不動産鑑定士の松本智治です。
前回に引き続き、私が不動産鑑定士になった理由をお話いたします。
エアライン・パイロットへの登竜門とされる航空大学校への受験の失敗から転じ、
都市計画的なものに漠然と憧れ、不動産分野では最高資格とされる不動産鑑定士試験を
受験してみようと考えました。
パイロットがだめなら、航空管制官にでもなれば良かったのでは?とよく言われますが、
私の性分です。
不動産鑑定士資格試験は、現在ではやや試験の形式は変わっておりますが、
私が受験をしました平成8年当時の内容でお話しを致しますと、
一次試験は一般教養試験であり、4年生大学卒業生(学部制限有り)であれば免除されましたので、
二次試験から受験を致しました。
内容としましては、「民法」、「経済学」、「会計学」、「不動産鑑定評価理論」の4科目について
論文形式で記述するものであり、あと「不動産に関する行政法規」科目は五者択一形式という試験内容でした。
やはり論文試験というのは、相当に記述に慣れないときちんと理論付けをして書き詰めることが難しく、
慣れるには相当に苦労を致しました。
約1年半、毎週末に高田馬場にある資格予備校に通って受験生活を送りましたので、
航空大学校への受験期間を含めれば、都合、約6年以上受験生活をしていました。
(その間に、宅建や行政書士、あと、土地家屋調査士なども受験しました)。
この頃の自分は、まさにいつ脱出できるのかも分からない氷河期の時代であり、
試験に受からなければならないというプレッシャーから、精神的にも常に不安定な時期であったと思います。
そして、「今度こそ、必ず、、、」という自分への追い込みが功を奏し、幸いにも一回の受験で
不動産鑑定士の二次試験は合格することができました。
合格掲示板に自分の名前を見つけた瞬間は、感動で手が震えたことを今でも覚えています。
さて、感動も束の間、不動産鑑定士試験はこの後もまだ続きまして、今度は三次試験を受けなければなりませんが、
三次試験を受けるには、まずどこかの不動産鑑定事務所へ実務経験を積むということで2年間の勤務経験を
経なければなりませんでしたので、横浜駅近くの鑑定事務所へ勤務することとなりました。
すると、実際の仕事の場においては、試験とは全く異なったさまざまな問題に直面し、
さらなる苦労を経験することとなりました。社会人経験も、自分にはありませんでしたので。
(次回その3に続きます。お楽しみに!)
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら