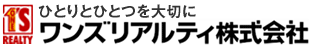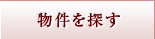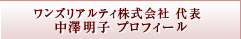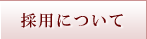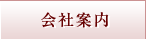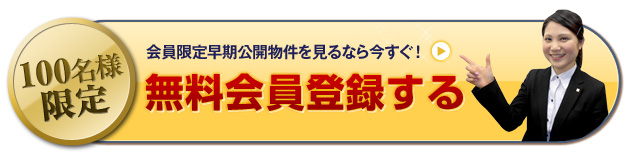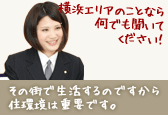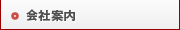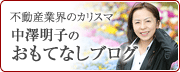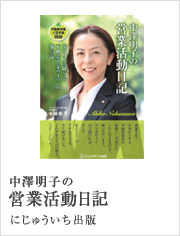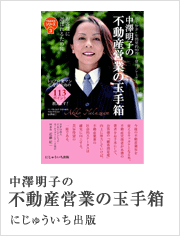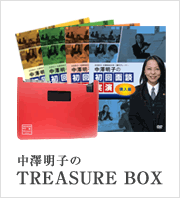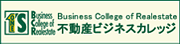皆様、こんにちは。西村友里です。
本日は、JR根岸線「石川町」駅徒歩2分にございます
店舗の内見立合いに行って参りました。
お客様は、今月初めに一度ご内見頂き、立地や環境をとても気に入っておられ、
今まで前向きにご検討を頂いておりました。
本日3度目の内見でしたが、今回は内装工事の見積り、消防設備の確認等を含めた
最終確認を行うためにご覧になられました。
こちらの店舗物件で学童保育(放課後児童クラブ)の営業をお考えです。
不特定多数の人に利用される建造物を「防火対象物」と呼びます。
「防火対象物」は大きく分けて2種類あります。
①消防法による制約をほとんど受けない「一般住宅(個人の住居、およびそれに付随する倉庫・車庫・農機具庫等)」
②消防用設備等の設置が義務付けられる「消防法第17条第1項の政令で定める防火対象物」の「政令で定める
防火対象物」
消防法施行令第6条“防火対象物の指定”により規定される建築物で、用途・面積・収容人員の差異より
必要となる消防設備・各種届出義務・防火管理者の有無などが変わるそうです。
一般住宅においては、建物火災による死者のうち、住宅火災による死者が約9割にも達することから、
消防法改正により、平成23年5月末までに住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
設置されていない住宅は違法となりますが、罰則規定は現在のところ一切設けられておらず、
また、住宅用火災警報器が設置されていない状態で火災が発生したからといって、
火災保険が適用除外されるといった制約も今のところはないそうです。
保育園・幼稚園等の児童福祉施設、養護学校・援護施設等の障害者福祉施設や、
病院等の火災が発生したときに避難等が困難であり、人命に多大な被害を出すおそれが十分にある施設は、
「特定防火対象物」と呼ばれます。
延べ面積により必要となる消防用設備等の条件が厳しく規定されており、消防用設備等の点検報告を
毎年行わなければなりません。
防火管理者の該当要件が厳しく規定され、一部の防火対象物においては、「防火対象物定期点検報告制度」が
義務づけられるなど、火災予防のための厳しい措置や規制が数多く掲げられているそうです。
今回のお客様も、消防法に引っかからないようにと、事前に消防署で確認をされたようですが、
「念には念を入れて、消防署の方に現地を確認頂きたい」とのご要望から、本日消防署の方に現地へお越し頂き、
店舗を確認していただきました。
消防署の方々は、テレビ等でよくみかける、あのオレンジと紺色の制服姿でお見えになり、お忙しかった様子で
20分遅れて3名でお越しになりました。
なかなかこのような場所で消防署の方を見ることはないので、とても貴重な体験をしたように感じました。
お客様も「なんだか緊張するね」とおっしゃっておりましたが、学童保育用の設備として「問題ない」といわれ
安心されておりました。
来週ご契約予定のため、しっかりと準備を行って参ります。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら