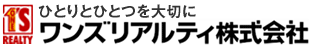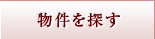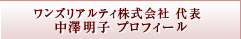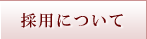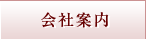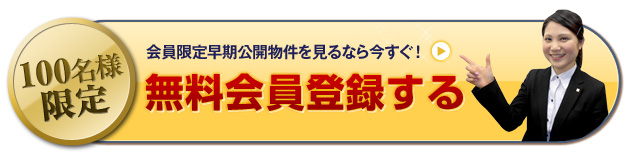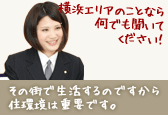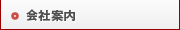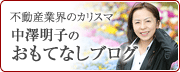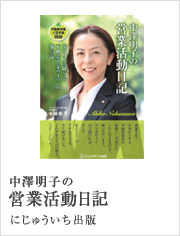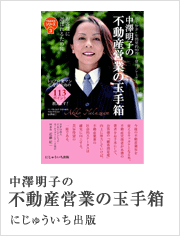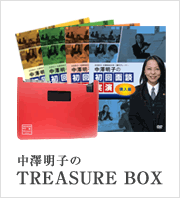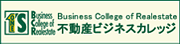皆様、こんにちは。山口幸夫です。
10月19日(月)より社内研修にて、
群馬県の薬師温泉旅籠「かやぶきの郷」へ行って参りました。
かやぶきの郷は、群馬県の草津・四万温泉に挟まれた旧草津街道沿いにあります。
私はその存在を全く知りませんでした。
そこは山々に囲まれたまさしく秘境の温泉といった場所で、
広大な敷地のなかに佇む歴史ある家屋に目を奪われました。
かやぶきの郷は、文字通り、かやぶき屋根の古来からの日本家屋が建ち並んでいます。
玄関口には長屋門(2階が展望台となっていてかやぶきの郷全体を見渡せます)、
メインフロアとなる本陣は、かやぶき屋根の長さが42m、かやの厚さが1mもあり、
全国でも数少ないかやぶき職人の手で作られたそうです。
他にも、人間国宝の陶芸家「濱田庄司」の居宅だった濱田邸、出羽の国の紺野家、
信州・諏訪湖一帯の豪農の末裔が築いた木村家、入母屋造りの小林家など、
全国のかやぶき家屋の名家が移築されており、郷の中はまるでタイムスリップをしたかのような光景でした。
その中でも私が心を惹かれたのが、時代もの展示処にあった日本全国から集められた「時代箪笥回廊」です。
全国各地から集められた薬箪笥、舟箪笥、水屋箪笥などその展示数の多さに驚かされました。
子供のころ、祖父母の部屋や親戚の家で見た箪笥に似たようなものもあり、とても懐かしく感じました。
箪笥の製作において、木の板を切り出す方法について小さな解説がありました。
丸太から板を切り出す時に、年輪の目に対してどの角度で切り出すかで、板表面の木目の様子が異なり、
板の強度や性質にも違いが出ます。
「柾目」「板目」という言葉を耳にされたことがあると思います。
「柾目」は年輪に対して直角に近い角度で切り出し、きれいな縞模様の表面です。
柾目の板は収縮や変形が少ない反面、水分を吸収しやすいという特徴があります。
また、丸太から取れる量が少なくなるため高価です。
「板目」は年輪の目に沿うように接線方向に切り出した木目で、不規則な曲線模様の表面です。
こちらは、収縮や変形しやすいが、耐水性が高く、液体を貯蔵する樽などには必ず板目の板が使われます。
日本人は箪笥や家屋など、ずっと木材を使ってきました。
木の特徴をしっかり活かしながら使用してきたことが良く理解出来ました。
不動産という仕事においても、木材の特徴を理解しておくことは大変重要なことです。
代表がこの地を研修地に選んだのも、歴史ある家屋を見学して学ぶという意味がありました。
今回の研修は1泊2日でしたが、本当にあっという間に過ぎてしまいました。
今年もあと2ヶ月余りとなりましたが、今回の研修で学んだことを仕事に活かして、
お客様ひとりひとりに満足を与えられるように、しっかり頑張って参ります。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら