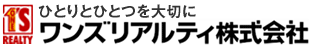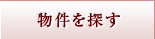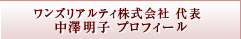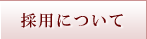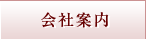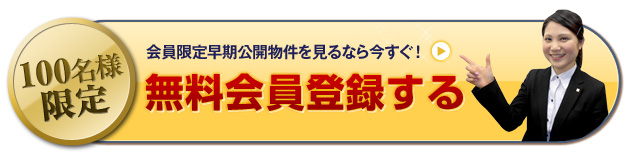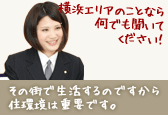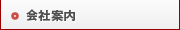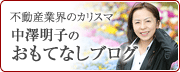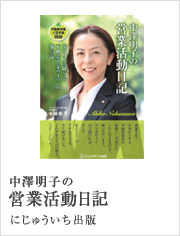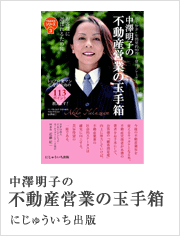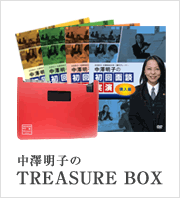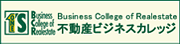皆様、こんにちは。山口幸夫です。
去る5月29日の読売新聞の朝刊の1面に、大変興味深い記事が出ておりました。
近所に商店がなく日々の買い物が困難な高齢者などの「買い物弱者」対策として、
商店の建築が原則禁止されている「第1種低層住居専用地域」で、
コンビニエンスストアの出店を条件付きで許可できるようにと、
政府が規制緩和する方針を固めたという内容でした。
戸建住宅が建ち並ぶ住宅街にコンビニ店が進出し、利便性が高まる一方で
街の風景が変わる可能性が出てきます。
建築基準法では「第1種低層住居専用地域」で建設できる建物について、
低層住宅や学校などの公共施設、小規模の住宅兼店舗などに限定しています。
私たち不動産会社がよく使う「閑静な住宅街」という言葉は、
概ねこの「第1種低層住居専用地域」のことを指します。
正直なところ、私はコンビニエンスストアの数は既に飽和状態になっていると思っていました。
少子高齢化に伴う人口の減少で、近くの大型スーパーマーケットなどが撤退したり、
商店街がなくなってしまったりしている住宅街は少なくありません。
一方で、セブンイレブンやローソン、ファミリーマート、サークルKサンクスをはじめ、
全国に存在するコンビニエンスストアの数は5万5000店を超えています。
それでも日常生活で買い物に不自由している高齢者は少なくないとのことですから
おかしな話です。
三井住友トラスト基礎研究所の調査によると、コンビニエンスストアからの徒歩圏(半径300メートル以内)に住む
65歳以上の高齢者の割合を推計したところ、東京23区では高齢者の86%が最寄りのコンビニエンスストアから
300メートル圏内に住んでいますが、全国平均では高齢者の徒歩圏カバー率はわずか39%に過ぎないそうです。
高齢者の61%が、徒歩でコンビニエンスストアに行くのが困難な「コンビニ難民」だと指摘しています。
郊外や地方ほど、コンビニエンスストアまで徒歩圏に住む高齢者の割合が低いということです。
併せて日本フランチャイズチェーン協会(フランチャイズシステムの健全な発展を目的として設立された
一般社団法人)は、この政府の発表に賛同をしています。
「地方都市などでは、近くのスーパーが閉店するなどで買い物が不便になっている地域があります。
その一方、高齢化が進んで最寄りの店まで行きづらくなっています。
そういった地域の住宅街で、コンビニエンスストアが出店できるようになれば、利便性も高まると考えています」と
歓迎のコメントを出しています。
今回のコンビニエンスストアの出店規制の緩和に、同協会は「まずは第一歩といったところ」として、
出店するには周辺住民の理解が得られることが「条件」なので、現実的には「なかなか難しい」とみているようです。
「たとえば徒歩5分圏内であっても、買い物に不便を感じる人もいれば、そうでない人もいます。
ビジネス街などでは、徒歩10分圏内に複数のコンビニがあっても、『もっと近くにあってほしい』という声があるほどです。
その一方で、静かに暮らせる環境を求めている人は多く、住まいの近くにコンビニができることに反対する人も
いるでしょう。周辺住民の理解が得られず、コンビニチェーンが出店を尻込みする可能性は否定できないということです。
閑静な住宅街において、街並みが変わってしまうという心配と共に、地方のコンビニエンスストアでは、
夜中に若者が集まって問題になったりもします。
しかし、今ではコンビニエンスストアは単なるお店ではなく、銀行のATMが利用できたり、
住民票などが取得できるように整備されてきました。
また、震災時に帰宅困難者への地図の提供など、自治体との災害時支援協定などもありますので、
その価値はどんどん高まっているといえます。
この第一種低層住宅専用地域(閑静な住宅街)へのコンビニ出店について、皆さんはどのようにお考えでしょうか。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら