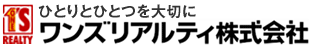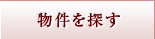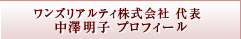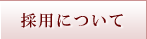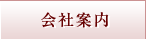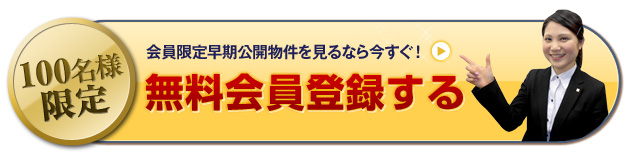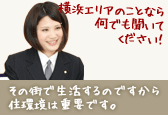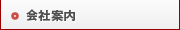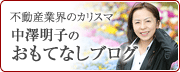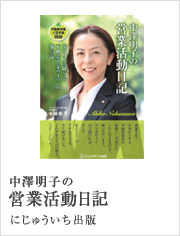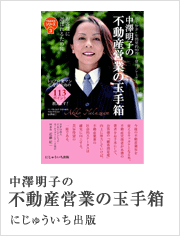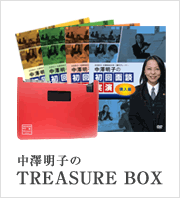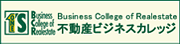皆様、こんにちは。山口幸夫です。
突然ですが、6月6日が「梅の日」だとご存知でしたか。
私も新聞の記事で知りました。
健康に良いといわれる梅干しや梅酒など家庭に欠かせない梅。
語呂合わせにもならない6月6日が、なぜ梅の日なのかを調べてみました。
天文14年(1545年)、日本中に晴天が続き、作物が育たず、田植えもできず人々が困り果てていました。
折しも6月6日、神様のお告げにより、時の天皇が京都「葵祭」で有名な賀茂神社に詣で、
賀茂別雷神に奉納して祈ったところ、たちまち雷鳴とともに大雨が五穀豊穣をもたらしました。
人々はその天恵の雨を「梅雨」と呼び、梅に感謝すると共に、災いや疫病を除き福を招く梅を「梅法師」と呼んで
贈り物にするようになったと言われています。 ※宮中日記「御湯殿 上の日記」より抜粋
この伝説から、2006年にJA和歌山県農が、梅をもっと知ってもらおう、もっと食べてもらおうという思いから、
6月6日を「梅の日」と制定したそうです。
梅は日本古来のものではなく、奈良時代以前に中国から伝わってきたそうです。
中国からは梅干としてではなく、梅の実を燻製させて作った「鳥梅(うばい)」と呼ばれる
薬のようなものとして伝わってきました。
梅の名前が記録に残っているのは、751年の『懐風藻(かいふうそう)』が最初といわれています。
また、梅は『万葉集』に118首も詠われており、これは桜の約3倍だそうです。
奈良時代、「菓子」というと「果物」のことを指していました。
梅は、梨や桃などの果物と同じように、生菓子として食べられていたようです。
こうして梅は古来から、食用として用いられてきましたが、その効用から薬用としても多く用いられ、
長期保存ができるため、非常用の常備食としても親しまれてきました。
梅の効能は数多く、インフルエンザ予防、胃がん予防、糖尿病予防、食中毒予防、動脈硬化の抑制、
血液浄化作用、疲労回復効果等は、科学的なデータに基づいて発表されています。
梅は人間の体の中で直接、血や肉となるものではありませんが、体の基幹部分すべてにエネルギーを与え
健康にしてくれるものです。
高齢化が急ピッチで進んでいる今の時代に、梅は健康管理に利用したい栄養食品といえます。
改めて、梅がどれだけ体によいものかを知ることができましたので、体調管理の一助として役立てて参ります。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら