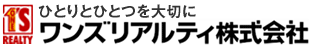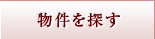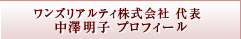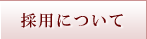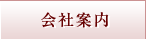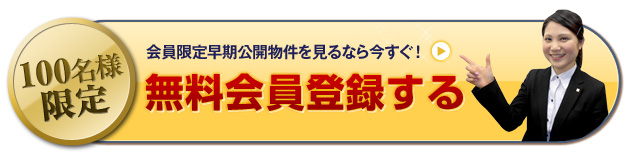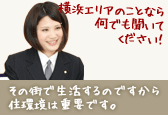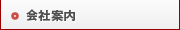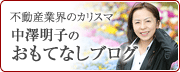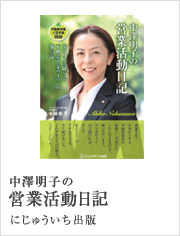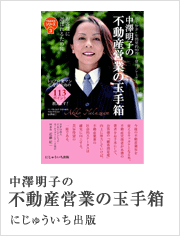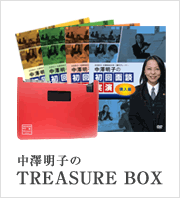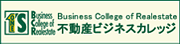皆様、こんにちは。管理部の牛迫宣機です。
“もう~いくつねると~お正月~、お正月には凧あげて~”
子供の頃はこの歌と共にお正月が来るのを楽しみにしていました。
そして、とっても嬉しかったのが「お年玉」をもらう事でした。
そこで「お年玉」について調べてみました。
「お年玉」の語源は、古くからの風習であった「年神様」に奉納された鏡餅を
参拝者に分け与えた「神事」が元だと云われています。
鏡餅は元々鏡を形どった物で、魂を映すものと云われており「魂=玉」で、
「年神様の玉」=「年玉」これに「御』が付き「御年玉」と称され、これを頂いた参拝者や家長が
家族や使用人等に分け与えたのが「お年玉」(もとは「年魂」と書いたとの事)の起源だそうです。
その後、お正月に親戚や知人を訪問する折、「御年始」、「御年玉」として
贈答品を持参することが風習となり、訪問先への贈答品「御年始」と、
お子様達へのお土産を「お年玉」と区分けする様になったそうです。
「お年玉」が、金品を贈る言葉として使われる様になったのは室町時代の頃からで、
江戸時代の後半頃からは、お餅が金銭に代ったとされています。
「お年玉袋」を「ポチ袋」と呼ぶ事が有りますが、この「ポチ」は、関西の方言で「心づけ、祝儀」等を
意味しており、専ら花柳界で芸妓さん等に与えていた「祝儀袋」の事だと云われています。
「ポチ」には、「小さな・これっぽっち」と云う意味が有り、「少ないですが」と云う謙虚な気持ちで与えたのが
始まりだそうです。
現在では、関西に限らず関東以北でも「ポチ袋」で通用するようです。
以前「お年玉」は、札ではいけないと子供の頃云われた事があると思いますが、
それは当時、未だ豊かでなかった時代の頃、子供達に平等に「お年玉」を分け与える為の
親たちの「苦肉の策」だったのではないかと思いました。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら