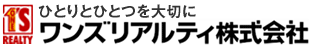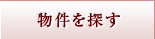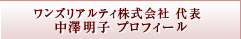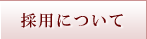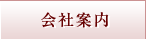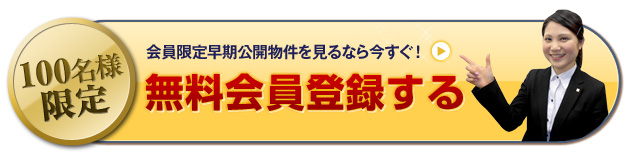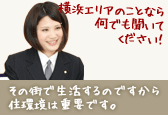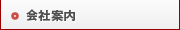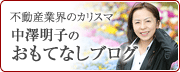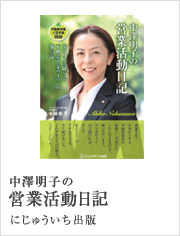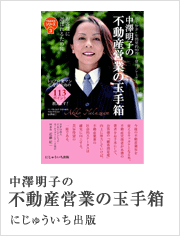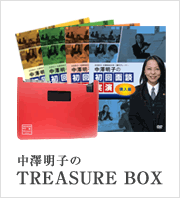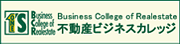皆様、こんにちは。山口幸夫です。
本日は10月4日(土)です。
私にとって土曜日は、倫理法人会のモーニングセミナーへの参加が、
いつの間にか義務のように感じるようになり、自然と何かしらの役目も頂戴して、
今日も少しブルーな気持ちでセミナーに向かったのでした。
しかし、本日のセミナーでの講義には大変感銘を受け、元気を頂いて参りました。
今日の日記は、実践の意義についてご紹介をさせて頂きます。
講師は、一般社団法人倫理研究所法人局 教育業務部主事 田口雄様。
テーマは「実践の意義」についてです
田口氏は、子供の頃から母親に連れられて、一般家庭倫理の会に参加していたそうです。
そこでよく言葉に出る“実践”という言葉の意味を大人に聞いたのですが、
その答えは、「ごちゃごちゃ言わずにとにかくやればいい」という返答でした。
ずっと疑問に思ってきた“実践”について、田口氏は下記のように教えてくださいました。
① 思う = その行動の先(結果)をイメージすること。人は思ってから行動している。
ただし、思うだけでは忘れてしまいます。記憶に残すために…
② 書く = 書いて、いつも目にするようにする。併せて、言葉に表す、ずっと言い続ける。
③ 良いこと・正しいことを行う = 良いこと・正しいこととは、万人幸福の栞にその定義が書かれています。
【真に正しい事とは、まず己が救われ、それと一緒に人が救われることでなくてはならぬ】
併せて、大変さの中で「明るさ」を忘れないことと教えています。
例えば、掃除が良い例です。大変でも明るく行うことが大切だということです。
重要なことは、自分も周りの人も幸せになるということです。
④ 続けること = 結果が出るまでやり続けること。目安は100日、100回です。
例として、お百度参りがあります。
やり続けた結果、その行動は習慣になります。
しかし、習慣は維持のみで、そこからの更なる向上は難しいため、
⑤ 次の実践に取り組む
この①~⑤のサイクルが、“実践の意義”ということです。
特に③の良いこと・正しいことの定義については、先日の日記で紹介させて頂いた齋藤一人さんが
言っている「大我と小我」の大我と、全く同じ定義でありますので正しくこれは、真理だと感じました。
早起きは三文の徳です。
しっかり頭に叩き込んで、この定義に基づいた“実践”を行って参ります!
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら