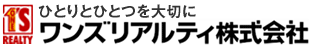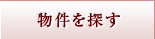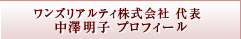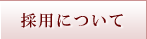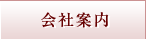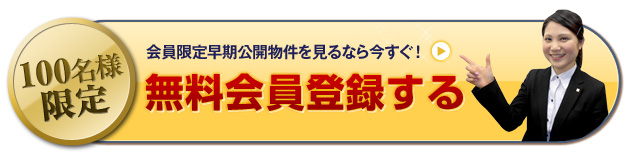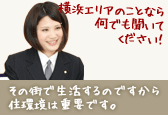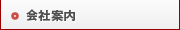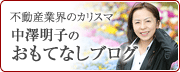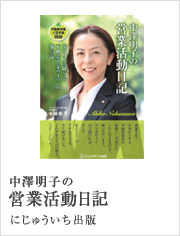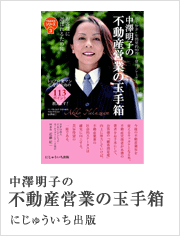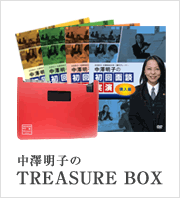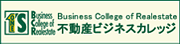皆様、こんにちわ。井上久恵です。
年末が近づいてきました。
弊社では、仕事納めの日に店舗の大掃除を
社員全員で行います。
その後、綺麗にした店舗にお正月飾りを飾るのですが、
今年は私が飾りを用意致しました。
鏡餅としめ飾りを準備したのですが、
なんと種類の多いこと・・・。
大きさもデザインも異なり、「あ~!!分からないー・・・どうしよう」と、
売り場で頭を抱えてしまいました。
その中からなんとか選び、自宅に戻ている最中、
「お正月飾りの由来とは・・・?」と徐々に気になってきました。
この機会にきちんと意味をここで知っておこうと思い、自宅に着いて早速調べてみました。
私が購入した鏡餅としめ縄について調べてみました。
①鏡餅
この名称は、三種の神器の一つ、「やたの鏡」を象ったものとも言われ、
神様への最高のお供え物とされている。
床の間に飾るようになったのは、室町時代以降。
江戸時代の鏡餅は、黒かったとか。(当時は黒米飯を常食としていた為)
鏡は円満を、開くは末広がりを意味する鏡開き。また刃物で切るのは切腹を連想させるので、
手や木槌で餅を食べやすい大きさに分解する。
②しめ飾り
しめ縄に縁起物などの飾りをつけたものをいいます。
代表的なものが、神様の後輪を表す「紙垂(かみしで)」、精錬潔白を表す「裏白」、
家系を譲って絶やさず子孫繁栄を願う「譲り葉」、代々栄えるよう願う「橙」などです。
しめ飾りは神様を迎えられる清浄な場所ということを示すために、現在では玄関ドアの
正面に吊るすのがならわしとなっています。
意味を知ると、行動が変わってきます。
今年は神聖な気持ちで、気持ちを正し、きちんと飾りたいと思います。
 店舗地図
店舗地図 お問合せメールはこちら
お問合せメールはこちら